
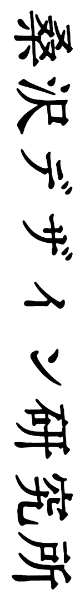
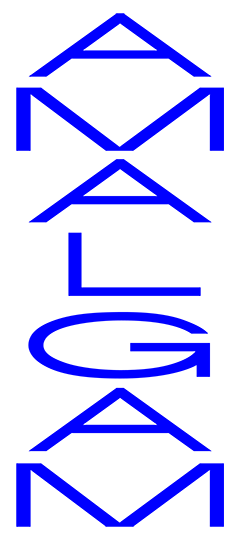
今回ご登場いただくのはアートディレクター、グラフィックデザイナーの奥村靫正さん。本媒体の他のデザイナーの方へのインタビューでもしばしばお名前があがるとおり、奥村さんの手がけた作品は時代の画期となるものが少なくありません。桑沢デザイン研究所の同窓生、眞鍋立彦さん、中山泰さんと結成したWORKSHOP MU!!でのオリジナリティあふれる作品の数々、デザインや文化を超え現象となったYMOとの試みはもちろん、広告やブックデザイン、DTPツールを効果的にもちいたビジュアルから十代のころから親しんだ日本画の再興、その多角的な経験と視点を通した提言など、この人こそデザインという境地に達した奥村さんのデザイン観に耳を傾けます。

奥村 興味をもつというよりは父親が日本画を描いているのを見て育ちましたので、自然にそうなったんですね。日本画の先生についたこともありますよ。基本は模写と写生でした。日本画は、ものを見て、それを描く「写生」と、絵をなぞりながら先人のテクニックをおぼえる「模写」の繰り返しです。それを高校生ぐらいまで10年ほどつづけました。
奥村 まあ反発です(笑)。親への反発からなにをどうしようというところからデザインに行き着いたんですね。
奥村 そのころになると、ポップアートや世界のグラフィックなどの情報が入ってくるようになるんです。ことに東京オリンピック(1964年)以降が盛んでした。展覧会に足を運ぶなど、そういった経験も大きかったです。
奥村 父や家族は日本画の世界でやってほしいということでしたから、反抗心もあっていろいろ画策した結果、桑沢へ進学することになったんですね。日本画の世界でやるとしたら、京都芸大や東京芸大の日本画科への進学を考えるということで、いちおう受験対策はしていました。結局受けずにデザインを学ぶことになりましたが、「この道でなければならない」というような強い決意があったというよりは、日本画の世界からどこまで離れられるかというようなことを考えていたというのが本音です。桑沢に進学した理由としては、写真弘社という会社の前の社長さんの柳澤卓治さんという桑沢出身の方と中学生ぐらいから家族ぐるみで懇意にしていただいたことが大きいです。
奥村 母方の親戚に尾崎三吉さんという写真家、歴史的にいえば、秋山庄太郎さんの前の世代のスターがいたんですね。戦時中から戦後の日本のメディアで活躍して、日本デザインセンターの写真部をたちあげた方で、そのような縁もあったかもしれません。僕の祖母が東京の奥沢在住なんですが、上京のさいに尾崎三吉さんの高樹町のスタジオに顔を出したりするなかで、写真やデザインに興味がめばえたところも少しありました。
奥村 国内外のデザインについては自分なりに勉強はしました。なかでも大正末期から昭和10年ごろに平凡社が出していた『世界美術全集』という30巻ほどの全集が自宅にあって、それが非常に面白い全集で、古代から現代までの海外の美術の動向と日本の美術が時系列に沿って並んでいるような編集でよく眺めていました。そこには当然、バウハウスなど、デザインの項目もあって、そういう情報は読み解いていました。受験では理工科系、千葉大の工学部には写真の学科もありましたから、そこもめざしていましたが、僕らのときは軒並み倍率が高くて、数十倍の倍率がザラだったんですね。芸大だと50倍か45倍もあったと思う(笑)。
奥村 国立の理工系志望ということで研数学館という予備校に通っていましたが、まわりがものすごく優秀なんですよ。そこでこれはちょっと厳しいかもしれないと。柳澤さんの助言にも、先生がすごくいいよ、というがありましたので、桑沢に志望をかえました。当時桑沢には、日本画の朝倉摂さん、彫刻の佐藤忠良さん、写真の大辻清司さん、それから僕が高校時代いちばん好きだったデザイナーの草刈順さんらが教鞭を執られていて、それも大きかったです。入ったときちょうど草刈さんは高島屋の宣伝部から西武の堤清二さんの要望でセゾングループのICを手がけられたころです。僕が好きだったのは高島屋時代の彼の作品でしたが、時代のトップクリエイターが学内にいらっしゃって、いま考えると、ほかの大学ではちょっとなかったと思います。
奥村 小さな学校ですからね。毎日なんらかの交流はありましたよ。僕がいた当時は1学科30〜40人くらいで、2年終えて、3年次は研究科になるんですが、そこでは12人くらいでしたから。
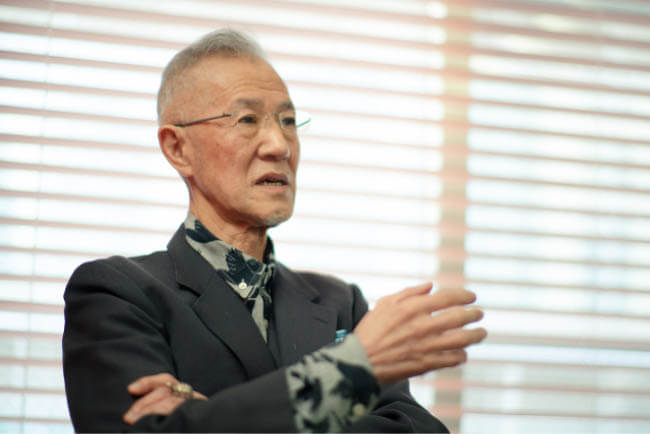
奥村 研究科では3人一緒でした。初対面の印象はおぼろげですが、たがいのものの見方を知って意気投合していました。最終的に研究科で一緒になりましたが、卒業して真鍋くんと中山くんがWORKSHOP MU!!を立ち上げました。
奥村 1年ほど、みんなそれぞれデザインの勉強をしようということですよね。リーダーの眞鍋くんなんかは桑沢の助手を1年半くらいやって、中山は代理店でアルバイトをしていました。僕はもうまったくのフリーランスをしていて、1年ほどでWORKSHOP MU!!に参加しました。
奥村 実家の両親や祖父がコレクターで、僕自身好きだったのもあって、骨董に関してはある程度の素地があったんです。骨董通りのお店で買い付けをはじめたときはまだ十代でした。市場に行ってオークションに参加して買い付けるんです。オークションではまず偽物は上がってきませんし、いいものにははじめからから値段がついてきますからそういうものを見て勉強するんです。
奥村 会社を設立して青山の表参道と246(号線)の交差点あたりのワンフロアを借りてはじめました。そのときはスポンサーがついていて、いろんな会社の商品企画の仕事をやっていました。家具とかファッションとかテキスタイルとか、いろいろでしたが、グラフィックではありません。その場所で2年ほどつづけたのち、1971年に埼玉県の狭山に移動します。ちょうど万博の時代で、1970年代の大阪万博を期に若者に投資する社会的な機運が高まって、当初仕事は順調でしたが、2年ほどしたらオイルショックがあってダメに。移転したのはそういう理由もありました。

奥村 狭山市がハウスを貸し出すという新聞記事をたまたま目にしたんですね。見に行ったら環境もよくて、すぐに決めました。それまでは都会のど真ん中でしたが、音楽的にも、ザ・バンドのようなカントリー志向のバンドが出てきたり、ウッドストック(のフェスティバル)があったりしましたから、すごく新鮮でした。
奥村 細野くんとはほとんど同時に引っ越してお隣どうしでしたから。自宅録音の試みはおそらく日本でもはじめてですよね。庭には大きな電源車が入っていました。リビングをスタジオにして、メンバーはキーボードに松任谷正隆、ドラムの林立夫、ギターの鈴木茂といった当時親しかったミュージシャン、そして奥さん、幼い子どもまでいました。だから毎日のように行っていましたね(笑)。
奥村 それも桑沢です。僕らの在学していたころは学生運動が盛んでしたから、学校を通さなくても校内でコンサートができたんです。まったくフリーだったんです。
奥村 そうですね(笑)。校舎でよくコンサートを開いていましたよ。当時は3階に教室があって、三つくらいのスペースに間仕切られているんですが、仕切りを除けると大きな室内になるんです。そこで券を売ってパーティをしていました。みんながそういうことをやっていたと思います。何回かつづけていると、やっぱり巧いバンドのほうがお客が来るし、券も売れてなりたつということに気づくんです。誰が最初に細野くんたちを呼んだのかはわかりませんが、自然にエイプリルフールが出演者に入っていました。小坂忠、細野晴臣、松本隆と、柳田ヒロというメンバーですね。そのようなことがあって、だんだんみんなと親しくなって、小坂忠がWORKSHOP MU!!に参加するようになったんですよね。彼は日大の芸術で、実家が彫金をしていたこともあって、絵心がありましたから。
奥村 細野くんや麻田(浩)さんなんかだと、彼らが来て「こんどLP出すから」と直接いわれるんです。狭山アメリカ村にはミュージシャンが何人か越してきて、空いたら知り合いに報せて、また誰かが入ってということの繰り返しでしたからみんなご近所さんなんですね。当時の日本のロックバンド、ある種の東京的なロックバンドのほとんどのジャケットをやっていたと思います。
奥村 東京郊外に環状に位置するアメリカ軍の基地、横須賀、横浜の本牧や厚木、それから横田、立川と狭山のジョンソン基地、その周辺のジャンクをあつかう店、クズ屋さんには1950〜60年代の本や印刷物が大量にストックされていました。そういうところから仕入れたものがMU!!のデザインの材料でした。当時、海外の古雑誌を売っているようなところは東京にはなかった時代です。仕事場で山のようになっている古雑誌や印刷物を元にコラージュしたりするんです。
奥村 5〜6年活動して解散、自然解散というのかな。それぞれみんな自分の道に進んでいきたいということになったんですね。グラフィックデザインをやっていきたいという気持ちは変わらなかったです。それからは、ムーンライダーズの『火の玉ボーイ』をはじめとして音楽関係のレコードジャケットを手がけながら、CFの制作、資生堂とかセゾングループなどのクラアイントの仕事、いろんなことやりました。音楽の仕事だけで当時の会社はなりたちませんでした。
奥村 ひどい状態でした(笑)。ほとんどのレコード会社はロックは売れるものではないということで、まったくお金をかけず、内製の予算でやっていくという感じでしたから。
奥村 僕の場合、もっとも考えるのは、相手の要求をいかに汲むかということなんです。ミュージシャンが相手なら音楽との同調性、企業であれば企業のブランディングに対して答えを返していく、その点ではやり方は同じといえます。

奥村 MU!!が自然解消してから、僕は狭山を離れ、原宿のセントラルアパートに「The Studio Tokyo, Japan.」を構えました。それまでに10年ちかいキャリアがあったんですが、おそらくそういうことをやる人があまりいなかったんでしょうね。当時、ほとんどのデザイナーは代理店にいるような時代でしたから。
奥村 そうです。それも直接ですね。それ以前も、ティン・パン・アレーとか、彼のまわりの仕事はつづけていました。YMOとの仕事は1981年、アルバムでいえば『BGM』や『テクノデリック』以降が中心になります。それまでもチームにはいたんですが、羽良田平吉さんとか横尾忠則さんとかが制作していましたね。
奥村 これは細野さんをはじめ、3人全員の意向で、いままでやっていたエンターテイメント性、自分たちが(ジャケットに)映っていて、ある種のアイドル化に拒否反応をしめしはじめたんですね。彼らは自分たちは写真を撮らない、という。一方、所属レーベルのアルファレコードは出てくれ、と口説く。そういう段階からはじまりました(笑)。
奥村 (苦笑)WORKSHOP MU!!の最後のほうもそうですが、自分たちがやりたいものが出てくるわけだから、やっぱり共同作業というのもなかなか難しくなってきますね。たしかに『BGM』のときは雰囲気がわるかったとよくいわれますが、僕の印象では、少なくとも音楽をつくっているときはそういう雰囲気はなかったですよ。

奥村 決まるまでの過程では、トーストにバターぬっている絵柄の案もあって、いくつか出したなかで、この画像におちつきました。
奥村 普通はありえないですよね。IC的にマークをつくるということは、YMOのような音楽アルバムでは前例がないので、あえてやってみたということです。三本の湯気がYMOを表すとか、つかれたので温泉に行きたかったからとか、いろいろな意見はありますが、僕としては自然に出てきたとしかいいようがありません。そのようにして生まれてきたアイデアを、クライアント、YMOの場合はメンバーと何度も話し合いながら、彼らの欲求に対して返していくなかでかたまっていくという感じですかね。
奥村 あれはね、編集作業がベースにはなっているんですね。グラフィックが先行するというよりも、台割りをつくってどのように構成するかという、ひとつひとつの流れをつくっていくんです。坂本くんがテーマを考え、それに対して図像を選んでいくという、完全に編集的な手法です。対話を通してなにが必要なのか考えながら構成していく——、僕の基本はむしろエディトリアルなんですね。
奥村 たぶんそれぞれのジャンルで専任でやっていた人がいなかったからだと思います。たとえば葛西薫さんは広告、戸田ツトムさんならエディトリアル——、そのような状況で僕はちょうど中間的な立ち位置だったのかもしれないですね。それぞれの分野で、その後もみなさんは進化していくんですが、僕の場合は区切りが曖昧で、そのぶん自由にやれたのかもしれません。
奥村 チェッカーズは秋山くんがもちこんできた企画ですね。音楽は歌謡曲的でポップなんですが、YMOのプロジェクトをそのまま流用しています。僕が提案したのはスタイリングです。彼らはヤマハが主催するアマチュアコンテストの九州地区チャンピオンなんですが、学生バンドのようなものでしたから、東京でデビューするにあたって、合宿してギターやベースやドラムスをおさらいすることになった。そのときの彼らはジーンズに革ジャンにリーゼントというほとんどキャロルと同じスタイルで、バンドとしてはこれでいきたいというんです。WORKSHOP MU!!はキャロルも手がけていましたが、僕と秋山くんはあまり興味がもてず、断って帰ってきたんです。ところが2週間ほどしたら郁弥(現・フミヤ)が来て、言う通りにするから——ということではじまりました。
奥村 とにかくチェッカーズという名前は変えたくないと、であれば名前に合わせようということで、僕がテキスタイルの柄を描いて、いくつかパターンをつくりました。デザインはコムデギャルソンにいった堀越絹衣さんですね。
奥村 ビジュアルとかスタイリストのような仕事もずいぶんしてきましたからね。資生堂の仕事もそうでしたし、まだスタイリストとかそういうジャンルであまり人材がなかったんですよ。スタイリストという名称もなかったような時代でしたから。

奥村 当日の朝からつくりました。でも早かったですよ。うしろの書き割りをつくって、新聞紙で小道具をつくって、3人であっというまでしたよ。午前中にはできました。それでブルーシートを敷いて、近所の製材屋で大量におがくずを買ってきて砂浜にしたんです。服は当時の日劇ダンシングチームから借りてきました。
奥村 マッキントッシュはいち早くとりいれました。戸田ツトムさんと僕と、ID(インダストリアルデザイン)の川崎和男さん、この三者が最初期にマッキントッシュをつかって制作をはじめたと思います。マックを導入したきっかけは、新しいテクノロジーを試してみたいというところと、グラフィックにデジタルという概念をとりいれていく、そのなかでものをつくっていくという考え方に興味をおぼえたのが大きかったんです。

奥村 10年ほど前ですね。音はビジュアルにくらべて格段に情報量が少ないので、まず音楽でデジタル化がはじまり、10年遅れてグラフィックがPCでできるという時代が、80年代の後半にようやく到来したということだと思います。
奥村 いちばん感じたのは情報量のなさです。その点ではストレスはありましたが、それも急速な進化をとげてフォトショップが出てきて、そこからいまの状況が生まれます。80年代末にDTPがはじまり、90年代末には出版の分野でも主流になってくる、その10年の飛躍は大きいですが、当時からデジタルには可能性を感じていました。当時は情報量こそ少なかったですが、技術的な側面での限界を感じたことはありません。むしろ現在のようなデジタルの世代がいずれ到来するという予感のほうが大きかったですね。
奥村 学生のときはいろいろなものを吸収するしかないということでしょうか。吸収するものによってだんだん自分がつくられていく。そこから進む道が生まれてくるような気がします。僕が桑沢に通っていた1960年代末は世相的にも騒がしい時代で、情報がかぎられていましたが、そのぶんひとつひとつが重力をもっていて、いまみたいにネットで「いいね」で終わっちゃうようなものじゃなかったんです。ものや出来事の存在感、そういうものにふれられたのは大きかったかもしれません。
奥村 その時点の発想につきますよね。つねに白紙の状態に戻してつくりこんでいく。まずなにもひきずらないで真っ白なところからテーマをつくっていくというものが、わりと自分のなかでは大きいですよね。
(2024年3月1日 TSTJにて / 撮影:塩田正幸)