
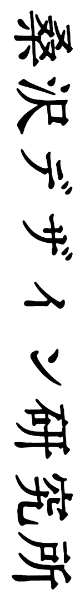
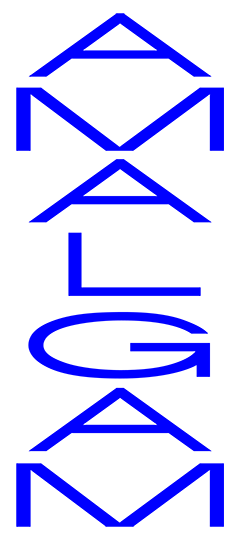
「本当に楽しんでいました」——桑沢デザイン研究所在学時を振り返った北山さんの発言にはあふれんばかりの実感がこもっていました。じつはこの言葉の前には「授業以外は」の文言があるのですが、いくぶん照れ隠しのニュアンスを含んでいるであろうことは、授業や課題を通して身につけた「手でつくる」感覚や、仕事に向き合うさいのていねいさが、現在のお仕事にも活かされていることでわかります。1990年代前半に一世を風靡した「渋谷系」の中心地「コンテムポラリー・プロダクション」で時代を象徴する数々のCDジャケットを手がけ、1998年にご自身の「HELP!」の設立を皮切りに、誌面や作品の背後にある「デザインすること」の核心に踏み込んでいく、北山雅和さんにお話をうかがいました。

北山 神戸生まれですけど、中学1年のときに父親が転勤で東京に移り、翌年に家族を呼んだので、僕も引っ越しました。中学2年で神戸から東京だったので、言葉が違うし、勉強もまったく違って大変でした。
北山 絵は子どものころから好きでした。きっかけはおそらく、小さいころに車とかオートバイとかが好きだったからなんですよ。あとはロボットものとか、そういうものが好きで、そうするとそれらを模写したくなるんですね。ほかにもプラモデルや粘土細工も好きでした。一方で、野球なども好きでずっとやっていました。動きもするし、ひとりでこもるのも、両方できるタイプでした。マンガも読んでましたよ。
北山 そんなにディープではないんですが、4年生か5年生のときに、『マカロニほうれん荘』でひっくり返りました。人生の書じゃないけど(笑)、人格形成に影響あったんじゃないかな。全然デザインには関係ない——あ、あるかな、少し。
北山 僕は全然遅かったです。高校を卒業したときに流れで受験した大学を落ちて、学部を調べていくうちに、たまたま近くにあった美大のパンフレットが目に入って、1年浪人して勉強するなら、こっちにしてみようかなという気にはじめてなったくらいですから。それで親に「美大に行くのはありでしょうか」と聞いたら「いいんじゃない」と。その後、代々木ゼミナールの造形学校に通いました。1年間勉強するうちに、デッサンは結構点を取れるようになって、多摩美と武蔵美と東京造形大の3校を受験しましたが、実際はなかなか難しくて、結果が出た後にまだ募集していたセツ・モードセミナーに行こうとしたんですが、予備校の先生が、桑沢の2次がまだ残っているということで、いいかもと思って滑りこみました。

北山 授業以外はもう本当に楽しんでいました(笑)。親の干渉もないし、時間はたっぷりあって、お金はないけど、成人してお酒も飲めるようになってからは、みんなで集まって飲んだりしていました。安い居酒屋に行けたらそれが一番の贅沢。でも学校のそばにはレコード屋さんや洋服屋さんも多いから立ち寄ったり、ぶらぶらすればなんでもあるじゃないですか。
北山 ヒップホップについては桑沢に入ってはじめて聴くようになりました。入学は1987年でしたが、当時ヒップホップはそんなに一般的ではなくて、本当に好きなやつが聴いている感じでした。校内では、ネオアコ好きな友だちがいたり、モッズっぽい人が集まったり、パンクのやつが集まったりしていました。でもみんな音楽好きだから、クロスオーバーしていくんですね。
北山 たとえばヒップホップなら、僕らのときはスチャダラが広めていったんですね。これは聴けると思うよとか。あと彼らはネタを探していたから、どういうレコードがいいんだとか、こういうふうなレコードを探していて、あったら教えてくれとか、情報を交換していました。
北山 クラブで遊ぶお金もないから学校でパーティをやったんですよ。機材を借りてきて、学校で場所を借りてやろうよ——みたいな感じで申請したらアトリエを貸してくれました。それでターンテーブル、スピーカーを持ち込んで、月イチくらいでパーティしていました。
北山 エイプリル・フールって桑沢でやったことあるんですか!? すごくないですか!? それ知らないですよ。はじめて聞いた。
北山 すごい、それは。歴史が立体的になりますね。
北山 当時はスカリバイバルがあって、学内にスカバンドがあったんですよ。そのベースが白根ゆたんぽなんですけどね。その一番人気のバンドの前座みたいなかたちで、スチャダラパーは最初にライブをしたはずです。でもまだすごく下手だったからブーイングが出ていました。もういいでしょ、もうやめなよみたいな(笑)。そんなこといわないでもう1曲といった感じのやりとりがステージと客席でありましたよ(笑)
北山 最初は4人なんですよ。ナイチョロ亀井(亀井雅文)くんがDJだった気がする。いや、ANIか。ターンテーブルはANIくんが買ったので、ANIくんがDJだったと思います。3MCで、SHINCOも最初MCでした。ビースティ・ボーイズみたいな感じで跳びはねながらサイドから出てきました。
北山 ひどかったです(笑)。客はみんなガチでブーイングしていました。だから市民権を得るまでちょっと時間がかかるんですよ。でも自信というか確信みたいなのがあったんでしょうね。カウンター的なというか、みんなやってないからやるみたいな気持ちはあったんじゃないかなとは思います。
北山 バラバラでした。僕は1年生のときはリビングデザインでしたが、1年次はグラフィック、インダストリアル、インテリア、全部やるんですよね。外にドレスデザイン科があったので、ドレスの子と、リビングの子と——みたいな感じでした。2年生からはコースによってバラバラになるんですけど、それでもまんべんなく全学科いましたよ。僕はリビングデザインから2年でグラフィックに進みましたが、ANIくんはドレスで、ボーちゃん(BOSE)はインテリアだし、あと白根もグラフィック。そんな感じでまんべんなくみんないろんな感じで、課題を手伝ったりもしました。
北山 いや、間にあわなさそうなやつの手伝い(笑)。提出日の2日前ぐらいからちょっとヤバい、となって、最終日はみんなで集まってもう徹夜です。僕は憶えてないけど、ANIくんが北山くんが手伝ってくれたっていうのを、『余談』という彼らの副読本で書いていました。
北山 桑沢といえばもう課題の多さじゃないですかね。僕らはめちゃくちゃ遊んでいましたけど、でもやっぱり課題は出さないと1年生から2年生に上がれませんから、及第点をもらうために、先生のダメ出しにもめげずにがんばりました。精度がわるいと〇がもらえない厳しい先生もいましたし、僕がいたときの桑沢はデザイン学校というよりは職人養成みたいなニュアンスが強かったかもしれない。平行四辺形の立方体をつくって、その貼り合わせのエッジが綺麗じゃないとダメという感じでした。木を削ってハンドスカルプチャーをつくったりするんですけど、磨きが甘いとダメ。何回も何回もトライして、オーケーが出るまでやるんです。彫塑とかも佐藤忠良さんに教えていただいたこともあります。「手でつくる」というようなことをおしゃっていました。個人的には、デザインを強く押し出されちゃうと、ちょっと敬遠していたかもしれないとも思いますが、職人的な技術はがんばるとできるし伸びますから。その点を鍛錬してもらった気がします。あと我慢強さ、忍耐強さも試されました。そういう意味ではよかったと思います。
北山 正直にいうと当時はデザイナーになりたいとは全然考えてなくて、まわりにも絵を描きたいとかイラストレーター志望の人が多かったです。当時ザ・チョイス展とかパルコの日本グラフィック展みたいな大きい賞を獲ってデビューする作家さんが、日比野克彦さんをはじめ、たくさんいらした。アートでも大竹伸朗さんがグワッと出てきた時期だから、もうみんなびっくりしちゃって、そういう人たちにあてられていた気がするんですよね。とくにグラフィックの連中はイラストレーターになりたいとか、作家になりたいみたいな人も多かったと思います。

北山 ロリポップ・ソニックについては、桑沢の後輩に好きな子がいて、存在は知っていました。ただ、「いい」といわれると、かえって警戒するじゃないですか。
北山 そのうちフリッパーズ・ギターが出てきて、どうやらロリポップ・ソニックの人らしいということでファーストを買いに行ったかビデオで見たか、どちらが先かは忘れましたけど、「フレンズ・アゲイン」に、これは大変だと。いろいろ調べて、信藤三雄さんという方がやられているコンテムポラリー・プロダクション(C.T.P.P.)がデザインを担当しているということを突き止めます。少し経って、たまたま学校のそばのレコード店「WAVE」に立ち寄ったら、桑沢の後輩がサクサクしていて、「いまなにしてんの?」という話をしたら、「じつはコンテムポラリー・プロダクションに入りました」というんですよ。ドレス科のめっちゃ遊んでいたやつだったからもうびっくりして。ちょうど中嶋佐和子さんという、フリッパーズを担当されていた方が辞めるあたりで、じゃあもしかしたら、と希望を抱くじゃないですか。それでちょくちょく彼と電話で連絡をとりあっているうちに、たまたま横にいた信藤さんが電話口に出て、遊びに来れば、と誘われたんです。そのときは信藤さんと2時間ぐらいお話ししました。ちょうど、アルバイトから社員に昇格して勤めていた会社を辞めようと思っていたころだったので、信藤さんには「連絡来るまで待っています」とお伝えしました。
北山 これはいろんなところで話しているんですけど、豆腐屋さんになりたいといっていた時期でもあって、その話を信藤にもしたら「豆腐屋かうちか(笑)」と。そしたら2ヶ月後くらいに電話をいただいて「バイトあるんだけど、今日来られる?」といわれたんですけど「今日は渋谷でスチャのライブがあるのでムリです。明日からじゃ駄目ですか?」と返事をしたら、もうゲラゲラ笑って「明日からでいいよ」と。それが93年の春でした。
北山 オリジナル・ラブが「クアトロ〇〇デイズ」みたいなのを仕掛けたのがそのへんだったと思います。フリッパーズが解散してちょっと経ったぐらいですよね。ピチカートも上り調子になっていた記憶があります。『ボサ・ノヴァ2001』の年だ。
北山 自分としてはコンテムポラリーで、ミュージックグラフィックがどういうふうにつくられているのか、そのシステムを目の当たりにしたという感じでした。レコード会社、ディレクター、アーティストとの絡みとか、撮影どういうふうにするかみたいなノウハウは全部コンテムポラリーで学びました。こんなに専門的にデザインの仕事が成立するんだなと思いましたね。
北山 信藤さんはひらめくのを待つタイプでした。ずっと洋書を眺めたり、レコード屋に行ってジャケット見て「これいい!」となってポンッと思いついたら、スタッフに振る。よくパクリ議論になりますけど、なにかをモチーフにインスピレーションがきて、ものをつくるという感じでした。映画をはじめ、ボキャブラリーも多かったし、いろんな引用があったと思います。信藤さんはふっと鉛筆で書いたようなものとか、サインペンで書いたようなものをデザインにポンと入れちゃったりするんですね。ポップアートっぽいというか、サンプリングアートっぽいですよね。もっと緻密に組み立てるやり方もあったとは思いますが、それがみていて面白かった。
北山 いや、あんまりなかったです。ただ、当時はまだピンセットを使いながら文字を組んだりしていたんですが、横に立って作業をみていた信藤さんに「もう少し小さくコピーして持ってきて」といわれて、用意して持ってくと、信藤さんが文字を組むところをすぐそばでみられるんですよ。ああ、そっか、そっちのほうがいいよな、みたいな感じで考えながら最初の2年ぐらいはすごしました。信藤さんがまだ自分でデザインしていたころですね。その後はもうアートディレクターになっちゃいましたが。
北山 信藤さんの采配。直感とあと適性みたいなのもあるのだと思います。ユーミンは一番年長者の人がやるとか。ちょっとロックっぽいのは誰々、おしゃれなピチカートみたいなものとか映画っぽいものは誰々、当時は男気系といわれていましたけど、ちょっと元気のある真心のような案件は僕で、コーネリアスも途中から僕になりました。トラットリアもそうですね。きっと信藤さんなりの適性があるんですよ。そこで受けたら、信藤さんがこういう方向でといってデザインを投げて、ラフをつくって、先方に出す前にいちどチェックが入ります。それからまた信藤さんとふたりで詰めて、提出して、直しがあるとその繰り返しです。僕は5年ぐらい勤めたんですが、最後はもうその段取りがちょっとしんどくなって、自信がついたのもあったので、相談のうえ……という感じで退社しました。
北山 信藤さんは会社を大きくしたかったと思うんですよ。辞めるのを伝えたときに、快く送り出してはくれたんですけど、僕にはこのデカさはちょっとしんどかったですし、もう無理だなと思っていました。僕は信藤さんがデザインしているのが好きだったから、そういうところに戻ってほしいなと思っていたんです。

北山 コンテムポラリーを退社したのはコーネリアスの『Fantasma(ファンタズマ)』(1997年)のジャケットやツアーパンフレットなどが一段落してからです。じつは独立のきっかけのひとつには1997年に子どもができたのもありました。子どもを持つと感覚が変わるというか経済観念も変わって、もうちょっとパーソナルに自分でこだわってやってみたいなという気持ちがめばえたんです。傾(かぶ)くのではなくて、削ぎ落とすというか、なるべくシンプルに、ということですよね。それまでの反動と、そこへのカウンターみたいなものもあったような気がします。気の合う仲間とかミュージシャンも出てきていたから、細々と言うのもあれですけど、こだわって一個ずつつくるというようなやり方をもういちどやりたい、というのが決断した理由でしょうか。
北山 小山田くんも子どもができたのがそのちょうどその後ぐらいだったから、そういう気持ちがあったんじゃないかな。
北山 そこは意識していました。30代という年齢のせいかもしれないですけど。

北山 信じられないかもしれませんが、僕の人生、本当にずっと綱渡りなんですよ。うちの娘には「奇跡だよ」といわれています(笑)。毎日、毎月、毎年が勝負で、気づけば、25年(笑)。なんかラッキーだったんですよね。きっとあの90年代があったから、この25年があったような気がする。
北山 そこまで器用ではないので、戦略は立てられないですけど。たとえば僕はちょっとロゴが得意だったり、デザインのスタイル的にロゴが多かったりしたので、そういうところに活路を見出すということなどは考えます。小山田くんが主宰していたレーベル「トラットリア」がサッカーのコンピレーションを出してくれたおかげで、テレビのサッカー番組のオープニング制作とかサッカー雑誌のアートディレクターとか、サッカー関連の仕事もあるんですよ。音楽がメインなんですけど、ちょっと横にずれた枝葉のようなものに生かされているというか、救われてきたような気はします。
北山 どうなんでしょうね。人には救われているなというか、いいタイミングでいい人に会うみたいなところは、振り返ってみれば、あったような気はします。
北山 彼が動く時にはモードというかムードが必ずあるんですね。小山田くんからは、こういう方向、こういう感じということもありますし、こういうビジュアルが好きなんだけど、こうしたらどうなる? といって、それをもとに発想を飛躍させて、おたがいにぎゅっとつめていって、これでいいんじゃない、と彼がいったらそれでいけますし、万が一そっちじゃないなと僕がわかったときは「いやこうやったほうがいい」「なるほどね」というような餅つきみたいな感じのやりとりをするとちょうどいい感じにはまるんですね。コーネリアス関係の映像では、辻川(幸一郎)くんや、中村勇吾さんとだと、もっと拡張した、ものすごいものもできるでしょうけど、僕のとこだけはふたりで話し合ってやっている感じなんです(笑)。
北山 よく「コーネリアスデザイン部」っていう言い方をするんですよ。その感じは……会社、ユニットというよりも、僕はビジュアルですけど、なんか長く続いているバンドみたいな気もしますね。コーネリアスの「音じゃない部門」。

北山 いまはデザインのためにデザインをするとか、クライアントのためにデザインをしなきゃいけないみたいなところからは少し心が動いていて、なにかを伝えるためにデザインを使う、自分の表現方法のひとつと考えている部分がどんどん大きくなってきています。クライアントワークはやらないと僕らは食べていけないので継続してやっているんですけど、やっぱりそこでもなにか伝えることができないのかなと常に考えている。デザインのためのデザインっていう言い方をしたのは、その問いでもあって、そういうものだらけになっていいのかということを最近、すごく考えるんですよ。デザイナーに憧れてデザイン学校に入ってデザイン事務所なり代理店に入るのはステップとしていいことなんですけど、デザインをしてご飯が食べられれば、終わりなのか、ということをすごく考えます。デザインにできることはもっと自由で、もっと多面的で、いろいろあるんじゃないかなっていうことをすごく考えるし、それと、ご飯を食べていくためにはどうするかということのバランスをみながら続けるということにいまはものすごく力を使っています。 「音楽のデザインをずっとやりたいです」というのはもうなくなったというか、この社会情勢をみているとそれだけじゃ生きていけないと思うんです。必要なことは必要なことでちゃんと表現をしたくて、そのとき僕のなにを使うかといわれれば、やっぱりデザインなんだけど、ゴールはデザインではなくて、デザインを使ってなにをするか、なにを問うか、ということなんです。それって当たり前のことなんでしょうけど、どうもなにか見過ごされてるように感じるんですよ。
北山 デジタルについては、技術的に優れてる方がいっぱいいるので、それをみてるのとか使うのは好きですけど、自分がそっち側に行こうっていうことはあんまり考えたことがないですね。やっぱりモノに落としたいっていうのがすごくあるので、ディレクションしてデジタルの仕事はしますけど、それももう本当に数えるほどしかやってない。
北山 1996〜97年だったかな。マックはおぼえるまでは大変でしたが、アップルは人格があるというか、直感的で入りやすかったですよ。ゲームっぽい楽しみとか、あとハードの感じやソフトの表現の仕方とかもよかったから抵抗もなかった。マシンに乗る感じがしました。
北山 それは師匠(信藤三雄氏)の影響もあると思います。
北山 相当気にしていますが、そこだけに陥りたくはないんです。とはいいつつも、やっぱり気にはしています。デザインでちょっとびっくりする部分とか、オチをつけたいというかね。パッケージを開けたときにみんながよろこんだり、びっくりしたりすることを結構考えています。その最たる人がコーネリアスですよ。
北山 まあ趣味の世界ですからね(笑)。もらった人が笑ってくれるといいなと。別に大上段からものをいうつもりはないですけど、ひとつのコミュニケーションじゃないですか。プレゼントをもらうとか、そういうのとちょっと似ているというか。であればやっぱりみたときにクスッとさせたいっていうのはあります。かっこいいといってもらうのもうれしいですけど、軽く笑ってほしかったり、あとは、へえーという驚嘆を、化学反応としてもう一個起こしたいというのはありますよね。感情なのかなんなのかはわかりませんけど、それが届いて、その人が能動的にそれを触ってなにかしたときに、ひとつ上がるというか。そういうことはやりたいなとずっと思っています。
北山 楽しんでもらいたいっていうのはあります。デザインというか視覚表現、視覚伝達にはまだまだ楽しむ要素があると思うんですよ。クライアントワークになってしまうと、杓子定規な感じに陥りがちですけど、視覚伝達ぐらいまで広げて考えちゃえば楽しむ要素があると思う。だから少しでもそういう部分を見つけてほしいと思います。そこに気づくのは本人の資質にもよるのでしょうし、淡々とデザインがしていたい方もいるかもしれませんが、デザインはデザインができてそれで終わりじゃないと思うんです。その後、それを届けた先、届けた相手がどう考えるかというところがいちばん大事だということを忘れないでほしいです。
(2024年3月9日 桑沢デザイン研究所にて / 撮影:塩田正幸)