
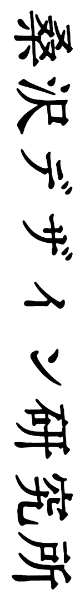
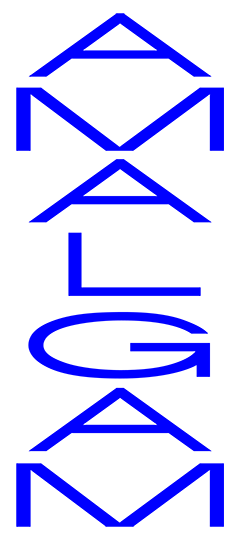
国内外の気鋭のブランドを視野に、独自の観点によるセレクトとミックスコーディネイトを提唱するk3、そのk3の自社ブランドG.V.G.V.(ジーヴィージーヴィー)のデザインを手がけるMUGさんにお話をうかがいました。フェミニンとマスキュリンが同居する世界観を土台に、形態はもとより素材にも徹底的にこだわりぬいた服づくりはブランドをたちあげ、25年を経た今でも根強い支持を集めています。ファッションにめざめた十代の頃から、自身のこだわりを自覚した桑沢時代、文化としてのファッションのあり方を再確認した現在まで、青山から奥渋へ移転した「grapevine by k3(グレープヴァインバイケイスリー)」で、MUGさんのブレないファッション観に迫ります。

MUG 幼少期から洋服が好きだったんですね。祖母が着物を仕立てる人で、母も洋裁が得意で刺繍などを家でいつもやっているような家庭に育ったのも大きかったのかもしれません。姉がひとりいるんですが、彼女が早くにファッションに興味を持ち始めたのも大きかった。姉は2歳上ですが、影響は大きくて、たとえば洋楽を聴くようになったきっかけも姉ですし、影響を受けて真似をするようなところがありました。姉が買っていた洋服の雑誌を見て、逆に私の方が好きになったんですね。小学生の高学年くらいです。
MUG 『an-an』を買っていました。当時の『an-an』は今とは全く違ういわゆる“Fashion誌”でスタイリストさんやモデルの方、メイクやヘアの方も含めていまでいう大御所の方が担当されていて、クリエイションがすごかったんです。私は当時まだ子どもでしたが、雑誌をみて、大人っぽさに憧れを抱きました。その後、『流行通信』や『ELLE』といった雑誌の大人っぽい世界に興味をもちはじめて、自分でもそういう雑誌を購入するようになって、そこから『i-d』、『The Face』等の洋書や洋雑誌にどんどん広がっていきました。
MUG 中学を卒業する頃にはもうデザイナーになりたいといっていました。いろいろみていくなかで、淘汰されて、洋服が自分の一番好きなものになったんでしょうね。
MUG DCブランドは私が高校生のときで、まわりのみんなも買いまくっていました。高校生からするとDCブランドは大人っぽいですよね。それもあって憧れでした。当時袋を持つのが流行ったじゃないですか。
MUG そう(笑)。それで「あっ!」みたいな。お互い何を買っているか、理解し合う時代だったと思うんですね。私は当時、大人っぽい服が好きだったので、ギャルソンのトリコの袋をもっていたら、みんなが「えっ!?」という反応をしたのをすごく憶えています。ギャルソンをもつというのはそういうことなんだと思ったんですね。それと当時はビギが好きで、デザイナーになりたいと思ったきっかけのひとつでもありました。当時子どもだった私からするとビギなんて、足を踏み入れるのも緊張するくらいで、おそるおそるお店に入って、洋服をみていた記憶があります。店員さん(当時のハウスマヌカン)も、すごく大人っぽくて憧れでした。

MUG 高校時代、とにかくファッションの道に進みたいと考えていたとき、美術の先生がファッションの道に進みたいなら、美大か桑沢という学校があるよ、と教えてくれたんです。それまで桑沢のことは知らなくて、ファッションなら文化服装学院だと思うんですが、私は美術も好きだったんですね。そのうち美大に進学するにはデッサンと平面構成の試験を受ける必要があるという話が耳に入ってきます。それはなんだろうと思いつつ、そういう予備校があるから、ということで、代々木ゼミナールの造形学校に通ったんですね。そこで人生がかわりました。私は当時、女子校に通っていて、気の合う友達もそれなりにいたんですが、当時はアメカジの全盛期。好きなカルチャーが微妙に違ったんですね。みんなのことは好きだけど、趣味の話はあまり合わない。代ゼミには3年の夏期講習から参加したんですが、そうしたらそこがカルチャーの溜まり場みたいな感じで「ここ最高に楽しいんだけど」となったんですね。通ってくる人たちと仲よくなって、話を訊くと、造形大学に行く、武蔵美に行く、女子美を受けるとか、いろんな人がいるなかで、桑沢のことを聞いて「面白そう、私はこっちだな」と思ったんです。
MUG カルチャーショックでしたよ。みんないろんなことに詳しいし、自分が知らない音楽のこと、カルチャーのことを知っているし、ライブにも足を運んでいる。そのときの友達でスタイリストになった人もいて、今でもつきあいがありますよ。
MUG たしかに当時はロンドンのカルチャーが大好きでした。私はどちらかといえばアングラなものやカルチャーが好きなんですね。たとえば音楽なら、ここにも姉の影響があるんですが、姉が後期パンクからカルチャー・クラブやデュラン・デュランなどのニューロマンティック勢のポスターを部屋に貼っていたのをみて、私も「このひとたち何!?」みたいな感じで聴くようになりました。当時はラジオをよく聴いていて、洋楽がいっぱいかかっていたから、必然的に洋楽中心で、UKロック、インディロックからクラブミュージックも好きでした。桑沢の入学後はバンド好きな友人がたくさんいたので、連れ立って渋谷のクラブ・クワトロや川崎のクラブチッタによく行っていました。
MUG 別の学科の友達も多かったです。学生ホールにみんなで集まって、あのバンドが来るよ──という感じでしゃべっていると、ひとつ上のお姉さん役の友達がいて、チケットとっておくよ、みたいな(笑)。毎日がすごく楽しかった。桑沢に行って、カルチャーのつながりでできた友達との交流で自分の好きなものが形成されていった気がします。
MUG 私は元来、人見知りなんですけど、自分と同じような境遇というか、目指しているものが同じとか好きなものが同じとなると、自分からも入っていけるんです。まわりは面白い人ばかりでしたから。

MUG ドレスデザイン科です。当時は2クラスでした。
MUG 1年生のときの担任だった玉川先生という方がいらして、私が卒業した頃には独立されたんですが、玉川先生の授業は印象に残っています。そう考えると、自分の人生にはいつも、特別な誰かが必ず現れて、その人に影響を受けながら生きているなと思うんですね。
MUG ただ私は音楽や映画やアート、いろんなものに対して興味を持っていますが、刺さったことを深掘りするタイプなんですね。のめりこんじゃうんです。広く知識を蓄えるというよりは、自分の刺さるポイントに対して徹底的に調べたりする感じです。好きなものの範囲が広いと思う反面、気づくと広さよりも狭く深くを追求している感じでしょうか。
MUG 実践的な学びというよりは基礎をしっかり学ぶという感じでした。実際に自分でパターンをひき、生地を購入し、デザイン画も描くんですね。それを先生に提出してオーケーなら、パターン進行して縫製の工程に進む感じでした。最初につくったのはシャツで、その後にタイトスカートというような流れでした。そこから自分でテーマを設けて、コラージュ、生地を貼ったようなデザイン画などでブックをつくり、最後に仕上がった服と一緒に提出するという授業でした。
MUG 私には大雑把なところとすごく細かいところが同居していて、縫いなどに関しては、異常に細かかったりするんですね。提出物では「襟の返しがすごくきれいにできている」とほめられたことがあります(笑)。襟先がギュッと細かったんですよ。ステッチの巾とか、曲がっていたらイヤだとか、どこかがほつれているのがダメとか、そういうこだわりがあるのだとわかりました。それは今もかわらないですね。
MUG アントワープ系のデザイナーはすごく好きでした。スタイリッシュでミニマルな側面があったと思います。ヴェロニク・ブランキーノとかラフ・シモンズとか、大好きでしたから。個人的には、削ぎ落とされた、ちょっとシャープな感じが好きなのかもしれないですね。
MUG ときおりフェミニンなものをすごくかわいいと思う自分がいる反面、ジャケットがけっこう好きなので、ドレスっぽいものにジャケットを合わせてみるようなスタイルが心地いいという感覚に通じるものかもしれません。すべてがフェミニンだと物足りないから組み合わせで、男っぽいものと女っぽいものをミックスしたいという気持ちが土台にあります。服づくりやスタイリングでも、甘すぎると違和感を覚えるというか。日本だと、どうしても「かわいい」──この一言で表現するのは日本のファッションに対しても申し訳ないんだけど、どうしてもボリュームがあって重心が下がっていることが多いと思うんですね。自分に似合っていればそれが好きになったのかもしれないですけど、実際手にとる洋服についても造形についてはボリューミーなものではなかったんです。ちょっと男っぽいほうがいいとか、スーツを着た女性が格好良いというところは昔からあるかもしれません。

MUG 卒業してすぐ、友人と3ヶ月ほどヨーロッパ全域をまわる旅行に出ました。海外に出ると、日本とはなんだろうと思うじゃないですか。帰国後もカルチャーショックからしばらく立ち直れなくて、当時は実家住まいでしたが、これではいけないと一念発起して就職しました。プリントや刺繍の版下をつくる会社で1年半ほど、絵を描く仕事をしたのち、友人の古着屋に入り、買い付けでロンドンの古着のマーケットに間近で触れることができたのはよかったです。その後、現在の会社を紹介してもらって、当初はデザイナー待遇ではなく入社したんですね。
k3はロンドンのマーケットデザイナーの服を仕入れて売っていたお店で、私はロンドンが好きでしたからぴったりだと思って受けたんです。当初はインポートの洋服の検品とか、ミシンができるのでやっぱりマーケットの服は縫製に難があることもあって、ミシンが落ちていたりするのを直す仕事に携わるなど、いろいろやっていたら、代表からそんなに服が好きならつくってみれば、といわれました。私が洋服が好きでいつも社内にある雑誌などをみていたからだと思います。

MUG なかったです。それならやってみようかなと思ったんですが、商品としての服づくりに携わったことも、そういう会社での経験もなかったので、とりあえず、メーカーで働いている人や服づくりに関係のある友達に連絡をとって相談しました。そうしたら「うちが使っている工場でよければ」と紹介してくれたんですね。そこからです、ひとりでデザインと生産をやるようになったのが。パターンも知り合いの人づてにお願いして、なんとか最初の展示会にこぎつけました。
MUG しばらくは展示会方式でした。当時お店に並ぶのが流行ったじゃないですか。雑誌では『mini』がもりあがっていた頃で、代官山周辺のショップに行列をつくって服を買うような時代だったんですね。うちがインポートで販売していたPPQというロンドンのブランドがあったんですが、そのデザイナーが日本でショーをやりたいということになって、代理店だったうちが引き受けたんです。そのとき一緒に(ショーを)やってみれば──という代表の助言もあって、代官山のエアで開催したのがG.V.G.V.のはじめてのショーでした。ブランドがはじまったのが99年なので、2001年あたりだったと思います。そのときもスタッフ全員ショーというものがはじめてで、モデルの方に出てもらうにも「オーディションというのがあるんだ!?」という状態でしたから(笑)、イチからつくりあげたショーでした。
MUG 好きだったからできたんだと思います。当時は朝まで仕事していても、眠いとかはありましたけど、大変だとはあまり思っていませんでした。忘れているだけかもしれませんが、楽しいというのはあっても、辛いと思ったことはあまりなかった。辛さを感じるのは、もう少し後、中期なんですよ。
MUG 具体的に何があったというわけではありませんが、ブランドをはじめてしばらくしてから、つくっていることに行き詰まりを感じたり、発表し続けることにもプレッシャーを感じたりしたことがあったんです。ブランドをやっていると売り上げのことも背負わなきゃいけなくなってきますよね。アシスタントのことなどもいろいろ考えちゃうと、自分が仕切っていかなければならない。その頃は朝まで仕事するような状況がずっと続いて、あるときわれに返ったんです。私はこのままこの状況を楽しんでつくっていけるのかなと深く考える時期がきたといいますか。
MUG 仕事ばかりだとプライベートの時間がなくなっちゃって、人にもあまり会えない状態になりますよね。ストレスを発散するところもなかったんでしょうね。久しぶりに展示会にきてくれた方と、MUGちゃんとも最近ぜんぜん会えなくなっちゃったよね、という話になったんです。そうしたらその方が「でも大丈夫、友達は守ってくれるし、会っていなくてもいつまでもつながっているから」といってくれたことをきっかけに、何かがスッと抜けて、もうちょっと頑張れるかも、と思ったんですね。
MUG 私はデザイナーですが、デザインしたからといって服ができるわけではありません。縫ってくれる方がいて、生地屋さん、パタンナーさんや工場の方がいて一着の服が形になるということを忘れちゃいけないと思っています。はじめてショーをしたときの、もう何も考えずに楽しんだあの感覚と、いろんな工程にかかわってくれる人に自分は支えられているんだということ。まわりの友達や、今でも展示会に来てくれて洋服を買ってくれる人たちも含めたつながりは、小さくてもずっと続いていくことを感じました。ものづくり、ことにファッションは表面的にはキラキラしていると思われるかもしれないけど、そうじゃない部分もいっぱいあると思うんです。
一方で、クリエイティブということでは最終的なジャッジをするのは結局自分なんですね。すべてがかかっていると思うと、本当にデザイナーってある意味孤独だなとも思うんですよ。孤独とみんなの力でやっているというのが表裏一体なのだと思います。

MUG 自分も年齢を重ねて、突拍子もないデザインを世の中に問いたいというよりは、着たいものにちかい、ギリギリのものをうちだすことが多いです。ちょっとやらかしているかなと思える服でも、自分でも着られるもの、着たいものをつくっているつもりです。
MUG 何かを重点的にリサーチすることはあまりないです。「こういうのをやりたいな」とか「こういうのがかわいいな」とか、そういうのがなんとなくあるので、それをとりあげて具現化していくといった感じでしょうか。そういいながら、じつは私、春/夏が苦手なんですよ(笑)。重衣料のほうが得意といいますか、素材でもウールやカシミヤなどが好きなので。冬になればあれこれ考えられるんですけど、夏となったときに、自分が夏に着るものって、タンクトップかTシャツとパンツと、ほんとうにシンプルなんですよ。そうなったとき「夏ってみんな何着るんだっけ!?」と思ったりするんです(笑)。秋冬は素材の楽しさがありますからね。今は日本も夏がすごく暑いから、洗えるということを優先的に考えると、サマーウールなどが昔に比べると対象から外れちゃって、使える素材がどんどん減ってしまうんです。
MUG そうなると思います。以前は私も服はクリーニングすればいいという考え方でした。ウールが好きだからっていうのもあるんですけどけど、今は「これは洗えないですよね」と質問してくるお客さんもいます。その言葉を拾っていかないと、結局自分の考えを押しつけることになりますから。そういうことも最近は考えるようになって、洗えて、楽で──といった考え方は以前よりはとりいれるようになりました。
 MUG もしそう見えているなら、率直にうれしいです。
MUG もしそう見えているなら、率直にうれしいです。
MUG モデルについては完全に私の好みです。それが「マスキュリン・アンド・フェミニン」であって、見た目も甘くて女っぽい人よりはGVの服を着せたくなる、シャープなビジュアルのモデルを選ぶ傾向があります。私はオーバーサイズも好きなんですが、周囲の男性にもGVの服を買ってくれるひとがいます。
MUG いわゆるインフルエンサー系の方をはじめ、いま割とデザイナーという職業と、ディレクターとのあいだの線引きが曖昧になっていると思うんですね。洋服の勉強をしてきたから偉いということでもないと考えるひとたちが存在感をもっているなかで、素材や縫製へのこだわりがどこまで、そしてどのような方に刺さっていくのだろうということはよく考えます。
MUG 素材については、いまのデザイナーはあまりこだわりがない人も多いみたいなんですね。素材よりもビジュアルがいいとか、コットンであれポリエステルであれ、自分がほしいものであれば、なんでもいいという感覚なのかもしれません。私は逆に最初に見るのが素材なんですね。素材が何かというのがいちばん気になるんです。
MUG デザインがしにくい時代ともいえますね。なんでもすぐに検索できてしまうし、世界に存在しないデザインというものがむしろ、あるのかなと自分でも考えてしまいます。けれどもそれを考えだすと服はつくれない。ただ、若い世代のデザイナーでも、すごいと思う人もいっぱい出てきていますから。いまは服が売れない時代といわれていますが、私たちの時代がむしろ洋服バブルだったとも思うんです。もちろん80年代、もうひとつ上の世代はもっとすごかったと思いますけど。
MUG 「すごい」と感心することはありますよ。これ以上何もないと思っていたのに、新しい解釈を入れてきたりすると、なるほどと思うこともあります。そうやって「洋服=デザイン」というものは更新されていくんだなと思います。
MUG 自分が本当に何が好きか、好きなものを信念を曲げずに貫くことがすごく大事だなと思います。私はある対象に対する異常なこだわりがあるんですね。ずっと同じものにこだわってしまう。それがあって続けられているわけで、ブレてしまうとこういう時代だからこそ自分がなくなっちゃうというか。世の中流行り廃りはあるとしても、自分が信じたもの、影響を受けてきたもの、自分が好きでもっているものとかは、信念を曲げずに崩さずに続けていくことが大事だと思います。

MUG 20周年のときはそれまでのアーカイブを編んで写真集をつくったんですよ。その作業を通して過去を洗い直してみると、自分の好きなものは、ぐるぐるまわっているだけなんだなということを強く感じました。とくに感じたのは型の部分です。ほぼ同じ型が何年か周期でかならず出てくるんです。
MUG ショーをやっていたときは、毎シーズン、傾向の異なるテーマでしたから「G.V.G.V.は毎回違うものをつくっている」というように思われていたんですが、ずっと一緒に働いている人とか、長いつきあいの友達にいわせると「MUGちゃんって、同じものがずっと好きだよね」ということになるみたいです。そういう声を聞いたときに、きっと私のクリエイションの根底にはカルチャーがあって、似たような体験をしてきた人とつながっているのかもしれないと思ったんです。
(2024年4月4日 grapevine by k3にて / 撮影:塩田正幸)