
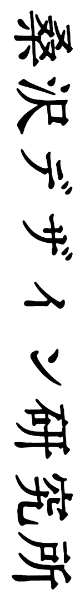
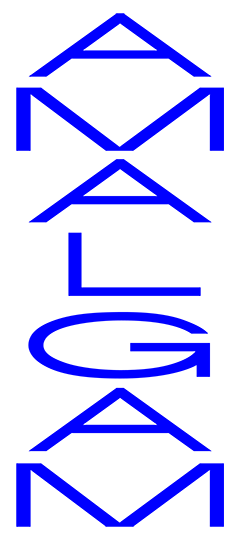
各界で活躍する桑沢デザイン研究所の先達をたずねるインタビューシリーズ、第1回はファッションデザイナーの研壁宣男さん。1999年にスタートさせたブランド「support surface」で機能性と審美性が美しく均衡を保つクリエションを世に問うてきました。そのスタイルをたとえるなら、ブランド名にさりげなく添えられた、「モダンでオーセンティックなのにオルタナティブ」という形容詞こそふさわしい。桑沢デザイン研究所を卒業後、ほどなくイタリアにわたり、言葉もままならないなかで服づくりを学び、やがてボディにまとわせた布地に直截手を入れる「立体裁断」を主とする独自の方法を確立する──。研壁宣男さんの来歴からデザインすることの原点を読み解きます。

研壁 最初は洋服ではなくて絵が好きだったんです。好きというよりも得意といえばいいでしょうか。昔の新聞の広告って裏が真っ白でしたよね。そこによく「ウルトラマン」の怪獣の絵を描いていました。それをまわりの人がほめてくれるんですよね。実際はたいしたことはなかったと思うのですが、おだてられてその気になっていました。小学校、中学校と、図画工作や美術は得意でしたよ。高校は普通科でしたが。
研壁 高校は地元の進学校で、1年生のときはだいたい真ん中辺(の成績)だったのですが、微分積分の試験で平均点をとって安心している自分と、高得点でも悔しがっているヤツがいて、ちょっとこれかなわないなと悟りました。美術方面に進もうと決めたのは高校2年生のとき。その時点ではなにになりたいかもまだおぼろげな感じでしたが、そのころちょうど、世にいう「DCブランドブーム」が起こりました。そうするとグラフィックやインテリアといったデザインの選択肢中にファッションが入ってくるわけです。ただ、進学を考えときにファッションの大学はその当時、ありませんでした。洋裁の専門学校はありましたが、僕のなかでは洋裁というよりはデザインとしてのファッションという捉え方をしていたので、進学先を調べるさいに、やはりインテリアデザイナーで有名な人、グラフィックデザイナーで有名な人、ファッションデザイナーでいま輝いている人の出身校を注目しますよね。そのなかで「桑沢」という選択肢が出てきました。
研壁 それと、時代背景としてはYMOの存在がありました。YMOのLPのレコードのグラフィックで奥村靫正さんのお名前をみかけたり、ヨウジヤマモトのブティックを当時、内田繁先生が手がけていたことも大きかった。じゃあ洋服で著名な卒業生は?と調べてみると、(桑沢は)小さい規模の学校ながら、活躍している方が多いのを知り、また、学校の創設者である桑澤洋子先生は意外にもファッションの分野の出身でもある。
親に対しても、ある程度敷居が高い進学先のほうが説得力ありますから。それもあって、高校3年生のときに美大予備校の夏期と直前講習で上京する機会を許されました。

研壁 僕ね、桑沢一本だったんですよ。高校3年生時でもう洋服しかないと思ってね。ドレス科の試験だけ受けました。
研壁 午前のデッサンの試験では「やった!」と思いました。午後の平面構成はまわりに明らかに自分より巧い人がいて「これはやばい、落ちるかも」と(笑)。余談になりますが、僕は予備校の直前の講習で学校が斡旋してくれた吉祥寺の下宿に泊まったんですね。そこにはほかにもたくさんの美大受験生が泊まっていて、たまたま隣の部屋の受験生と話す機会があって「どこ受けるの?」と訊いたら、桑沢だというので「一緒じゃん!?」みたいなことになった。それが吉岡(徳仁)だったんです。
研壁 はい。彼はリビング科を受験したはずですが、合格発表がドレス科のほうが早かったのにもかかわらず、一緒に来てくれて、先に受かった僕は「じゃあね!」といって帰郷したんですが、入学式でばったり再会するんです。
研壁 印象に残った授業はありますが、そのことよりも、昔の校舎がデザイン的にすごくよかった思い出があります。外見が格好いいとかではないのですが、3階建てで教室がベランダ越しに横縦全部繋がっていたのです。当時はファッション科で2クラスありましたが科にかかわらず、その行き来とか校舎内の縦の行き来とかも自由で開放的で、学科や学年を超えた交流が生まれ、フリーでいいなと思っていました。
研壁 行ったり来たり。それがまず、桑沢のよかったなと思うことですね。
研壁 いま、仕事で繋がりはありませんが、学生時代の友だちはいまでも腹を割って話せますね。
研壁 僕は1年2年を経て、「研究科」という3年次のコースに進学しますが、2年生次にロメオ・ジリというイタリアのデザイナー存在を知り、衝撃を受けました。当時はファッションでいうとまずはパリ。ゴルチェとかモンタナとかミュグレーとか、どちらかというと劇場型コレクションを発表するパリのデザイナーに代表されるファッションのイメージがあり、それに対してミラノはどちらかといえば、生産拠点、はなやかなパリに対して地味なミラノというイメージをもっていました。そんななか、対照的なロメオ・ジリのシンプルでモダンな空気感に、憧れをもちました。

研壁 「やられた感」。同じように感じた人はおそらく世界中にいたと思います。当時のデザイナーたちがうすうす感じたり思ったりしているけど表現しえなかったことを具現化していると感じました。
研壁 たしか雑誌の『ミスター』か『ミスターハイファッション』に、学校の同期の人が集まって対談するという主旨のコーナーの桑沢卒業生の回で、当時イトキンでロメオ・ジリのライセンス生産を担当されている方が出席されていたんです。その方を訪ねていったら、こころよく面会していただいて、作品もみていただいたうえで、当時ロメオ・ジリと契約していた高島屋の要人をご紹介いただきました。その方に相談しているうちに、そんなにやる気があるなら、ということでミラノでの面接の機会をもうけていただきました。
研壁 研究科はすでに卒業していました。それもあって、面接用につくった実物10着と片道切符でミラノに向かいました。面接では「あなたの作品はすごく気に入りました」といってもらえました。絶対お世辞だと思うんですけどね。「ただあなた、英語かイタリア語話せますか?」っていわれ、いや、話せないです、と返事をしたら、「だったら勉強してから来なさい」と。そりゃそうだなと(笑)。とりあえず勢いで来ちゃったけど、それ以外のことはまったく考えていませんでした。
研壁 面接で、ショーの招待状をあげるから来なさいといわれて、パリのショーを見せてもいただきました。パリには日本の書店があるのを知っていましたからその書店に行き、『地球の歩き方』の留学特集を立ち読みして、短期の語学留学で授業料が安価なところをみつけて、パリから直截学校のあるペルージャへ向かいました。
研壁 切羽詰まってましたから(笑)。お金ないしね。ペルージャでも、たまたまみかけた日本人の留学生の人に入学手続きを手伝ってもらって、3ヶ月の語学研修コースに入学しました。修了後にはミラノに戻りましたが、3ヶ月でしゃべられるほど、簡単ではなかったですけど。
研壁 ロメオの会社に電話しました。「前に面接していただいたノリオといいますが、憶えてらっしゃいます?」と責任者の人に伝えたところ、会社に呼ばれて「明日から来なさい」と。そのころロメオは刺繍に凝っていて、いきなりトレーシングペーパーで図鑑のイラストを布地の上にどのように刺繍するのか、配置とかをデザインしてくださいといわれたのが勤務初日のミッションでした。結局終電を逃してタクシーで帰りながら、ミラノでもファッション業界は忙しいなと思ったんですけど、そんなことは後にも先にもその一回きりでした。
研壁 アトリエには当時、世界からいろんな人が集まっていました。総勢10人はいたと思いますが、割合はイタリア人が4〜5人に外国人が4〜5人といった感じで、そのなかにはアレキサンダー・マックイーンもいました。勤めはじめて驚いたのはボディが置いてなかったこと。パターンを引く人が見当たらなかったんですよ。みんななにをしていたかというと、アイディアソースの写真や、デザイン画を、ロメオに提供するんです。僕もあるとき、ロメオからカットソーのデザインをやってくれといわれて、はりきってデザイン画を200枚ぐらい描きました。
研壁 デザインを見せてといわれて、机に並べるけど全部は乗りきらない。彼も、デザイン画の量に少し驚いたらしく、わかった、わかった、家で見させてもらうからといって持ち帰っていました。彼ね、デザイン提出の期日がくると、2週間くらい家にこもってアシスタントが集めてきたリサーチワークをまとめてデザインを完成させるのですが、最終的な彼のデザインを見たときに僕のアイディアが入っていたのを確認したとき、自分の居場所ができたように思いました。その後、2年ほど勤めて、カルラ・ソッツァーニの10CorsoComo(ディエチコルソコモ)に移りました。
研壁 言葉の面では1年ほどで相手のいっていることがおおよそ理解できるようになりました。しかし、自分では話せないんですね、まだ。その時期には仕事は、まわりがなにをやっているのか表情で察し、二歩先、三歩先を動いて、それでやっとみんなよりもちょっと遅いぐらいでついていける感じでしたから、体力、メンタル的にヘビーでした。相談できる友だちもいないし、きみはどうしてそんなに無口なの? といわれても、話せないだけなんだけど……みたいなことさえいえない(笑)。当時の同僚は、無口でコツコツ真面目だよねというイメージを僕にもっているかもしれないですね。
研壁 ただ働かないと食べていけないんですね。
研壁 中途半端で帰ってくるのは僕のなかではNGでした。そもそも日本に帰ったところで東京で暮らすあてもない。イタリアの通貨リラは安く、円が高いため、お金はまったく貯まらない。どん底からのスタートなのでつらいのは当たり前。成長するしか道はないので、つらいなりにポジティブな未来しかなかったです。

研壁 僕ももともと性格的に行動的なほうではありませんが、地方出身ですから、きらきらした都会やヨーロッパに憧れがあって、興味本位に動けたのかもしれない。僕らは、白黒テレビがカラーになったり、手回しで脱水していた洗濯機が二槽式になったり、発展が目に見えていた時代に育ちました。所得もどんどん増え、右肩上がりの時代に育ってきたのでポジティブ感しかなかったような気がします。それもあって、比較すると、いまの若い世代の全体的な空気感はちょっと大人しい気もします。それにいまパソコンとかスマホとかがあって、リサーチひとつとっても、図書館まで行かなくてもその場でできてしまう。海外旅行に行かなくてもハイビジョンの映像を見ると、行ったような気分になれる。実際に行ってみるともっといいかもしれないと頭のなかではわかっていても、満たされてしまう部分が多いのかもしれない。コロナ禍の影響も無視できないですよね。いま在学している学生はまだいいのかもしれないけど、2〜3年前だと、学校はもちろん、外出さえままならなかった。
研壁 桑沢の授業で、学生が、3Dで布を着せるようなシミュレーションをしてパターンがつくれるソフトがあるというんですね。「これやった方がいいですか」という質問があったのですが、僕はやっぱり布を扱うには、重量感っていうのかな。重みを感じなければいけないと思います。もちろんアプリケーションとか、アイデアのパッチワークでデザインができるような時代になってきているのもわかっています。でも、もしスペシャリストを目指すなら、みんながやっているようなことをやってもみんなと同じレベルにしかならない。もっと上に行きたいなら、実際に肌で触れて重みを感じてやっていかないと、より高いレベルには到達できないと、学生には応えました。
研壁 もしそれを望んでいるのであれば、ということではありますけどね。上面でなぞるよりはリアルに布に触れるほうがいいと思う。あとは、それが楽しいかどうかですよね。時間を忘れるくらい楽しんで最終的に他人が見たら努力しているように見えるような状態が一番身につくことだと思うんですよ。
研壁 僕はイタリアに15年ほど暮らしましたが、向こうの人が僕にたいして望むのは日本人らしさなんですね。海外にいると、アイデンティティといいますか、自分はどこから来て、なにをすべきなのかと考えることがあります。そのとき、僕には日本人の美的感覚があるけれども、海外での洋服の作り方も身につけている。これをミックスできるのは自分しかいない──、と感じたのです。洋服における立体的な考え方と、着物をはじめとした和服のように、人が着てはじめて立体になる服のシワの寄り方、布のもつ色気のようなものをミックスしたいと考えました。そのときの微妙なニュアンスは絵で表現するのはちょっと難しいとも感じました。イタリアで服づくりをする場合、デザイン画を描いたとしても、パターンを引くのはイタリア人です。それなら自分で原型をつくらなければ、と考えました。そのためにはデザイン画から洋服を発想するのではなく、立体からの発想というコンセプトを立てました。実際やってみると、デザイン画を描くよりもスラスラできたんですよ。桑沢で立体の授業をみっちりやった記憶はないんですが、仕事でトワルや人体に着せてチェックや仮縫いをしていたときの、手の動きと分量感を身体が憶えていたのですね。
研壁 アイデアが湧くというよりも手が動くんですよね。服は3Dです。3Dを2Dのデザイン画で表現するのは難しいと思うんです。陶器をつくる際にロクロでまわしながらいろんな角度からみてつくっていくじゃないですか。そういった意味のモデリングっていうのかな、それはやっぱり実際の大きさで布と対話しながらやっていくほうがスムースですね。それに、自分でやらないと微妙なニュアンスは実現できない。
研壁 学校などで、シンプルなものが好きで、シンプルなものをデザイン画で提出しても、先生には「デザインしていない」といわれることが多々あると思います。微妙なニュアンスの襟の返り具合こそがデザインと考えているのに、絵では微妙なニュアンス、立体の色気はなかなか表現できない。立体を平面でデザインしようとすると、どうしてもあるべきものをあえて変形することがデザインであるというような逆説に陥ることが多いと思います。
研壁 80年代はユニークがオシャレな時代。いまもそうなのかもしれませんが、僕が追求する服とはちょっとちがうと感じています。
研壁 まったくちがいます。デザインは売ることが前提ですが、アーティストは売ることを前提にしてないと思うのです。
研壁 そうです。人に買ってもらう、購入してもらうというのが大前提にあるというところですね。だから僕は新作に関しては作品という言葉は出てきづらい。「商品」といいます。ただ過去のものは、商品とはいわないですね。「過去につくったもの」という。

研壁 学生のときから、いつかひとりでブランドをやりたいと思っていましたが、結局なにをつくるということがみえないと意味がないとも思っていました。オリジナルブランドをつくることが目的ではありません。オリジナルである意味、内容がともなうべきです。
悶々としている時期は長かったですが、あるとき、明確にこういうのをやるべきだ、自分はこれをやるべきだという疑問が形になる瞬間が訪れたのです。
研壁 僕の場合、テーマというわけではなく、キーワードなんです。最初にテーマがあってテーマに沿って服をつくるという感じじゃなくて、最終的にできあがったコレクションを振り返ったときに、自分はなにを思ってやっていたのかというフレーズを探ります。
今回のキーフレーズ「KAWAII!?-Adorable」については、なんでもかんでもカワイイを連呼する(特に女性の)語彙力の貧相な感じもあって、本当に嫌いな単語でした。なので、いままで自分でカワイイを意識してモノづくりをしたことがなかったのですが、今回のコレクションでは自分が思うかわいらしさとはなんぞやという、自分なりのカワイイの具現化だったのかと思います。
研壁 立てません。徐々に湧いてくるっていうのかな。最初からこういう感じでいこうとなんとなく思っていても、実際手を動かしたりするとまったくちがうものになってくる。なかなか頭で思い描いたようにはいかないのを自分でもわかっているので、だったらそのときの感覚に任せようということです。
研壁 なりゆきは、コンテンポラリーでありえるための重要な手段です。通常はデザイン画が完成予想図。それに向けて作業を進めるわけです。僕はデザイン画があったとしても、完成予想図でなくてよいという認識でいます。実際の作業中に直面するいろいろな問題、あるいは湧いてくる新しいアイデア、それらを活かす。最終的には、いい服、いい形になればいいわけで、デザイン画にこだわるよりは、生き生きとしたアイデアをどんどん取り入れていく。ハプニングと出合い、ハプニングを活かすというのかな。
研壁 道草でえるものは大きかったりします。だからプロセスは省いてはいけないと思います。正確な回数はわかりませんが、ひとつの型で、その組み立て、直しの作業を20回から30回はくりかえします。もやもやした朧げなイメージを徐々に明確にしていくイメージ。またコレクションは新型が30〜40型ありますが、1型を完成させてから次のデザインに移行していくのではなく、デザインの余白を残しながら次のデザインに着手していきます。すべてのデザインを完成に向けて同時進行させていきます。
自分でやったものを客観的にみることは、なかなか難しいものです。そのための唯一の手段が時間を置くということだと思います。ずっとひとつのデザインにのめり込むと、自分に努力賞を与えてしまいがちで、客観的な視点に欠けたデザインになってしまいがちです。

研壁 ちょっと前なら、こういうふうにしたい、ああしたいというのはあったかもしれないですけど、いまはそれよりもつづけていくことに結構なパワーが要ると感じます。現状維持にはパワーが要るけど、現状維持の努力は後退にしかならない。それくらいの時代になっていますよね。
研壁 社会情勢というよりは、ファッションという業種、業態ですね。つねに消費者は新しいものを望み、市場はつねに新しいネタを探しています。僕のブランドは新興ブランドではなく、ネタ的には新しくはないわけで、つねに新鮮な提案をつづけていかないと、鮮度が保たれません。作り手が新鮮に思うことが、消費者にとって新鮮ではないこともありえます。それも残酷なところではありますが、その点においても客観的な視点はつねにもっていなければいけません。多くの製品が平均化し、簡略化、合理化された生産背景でつくられた、特徴のない、ほどほどの、安価なものが市場の大半を占める現在、本来あるべきクリエーションの精神、過程で値段以上の満足感を消費者に与えていかなければいけないと思っています。
(2023年11月17日 support surfaceにて / 撮影:塩田正幸)