
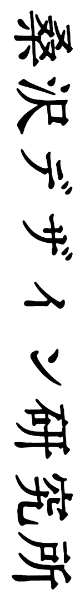
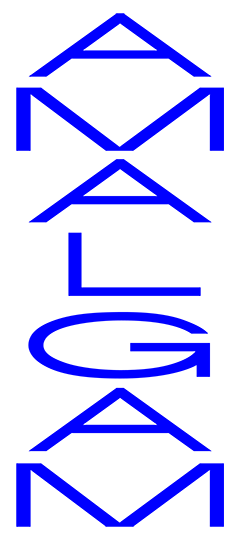
ベテランから新規まで、多くのファンを惹きつけてやまないブランド「ジェーンマープル」を1985年にたちあげたのが、今回ご登場いただくデザイナーの村野めぐみさんです。ファンタジアを探究しつつも、一義的なスタイルにとどまらない多彩さを有するクリエイションには細部にいたるまで、村野さんのものづくりへのこだわりが詰まっています。原宿の街が教室がわりだった中高生のころ、服作りへ自信がめばえた桑沢時代、渋谷系はなやかなりしころ、ファッション誌をにぎわせたタイアップ企画から、ブランドイメージを確立した現在まで、わくわくすることを忘れない服作りについて、村野めぐみさんにお話をうかがいます。

村野 実家は大田区で、学校は四ツ谷でしたが、中高と制服がない学校だったんですね。友だちのお姉さんがとてもおしゃれな方で、よく原宿に行っていたのもあって、友だちづてに、いま原宿がすごく面白いと情報が入ってきたんです。好奇心も手伝って、中学くらいから原宿に通いはじめました。登校前に原宿の花屋さんでアルバイトしたり、帰りにも立ち寄ったり、とにかく原宿という街が好きで、そこに居たいと思っていたんです。当時の原宿にはファッションもありましたが、大人の街でもあり、エモーショナルなもので満ち満ちていました。
村野 意外とそれは……図々しかったんでしょうね(笑)。物怖じしなかったんだと思います。レオンっていう喫茶店があったんですよね。
村野 レオンに最初に入ったのは中学2年生くらいのときでした。中高が6年間の一貫教育の学校だったので、上の方に先輩がいらしてそういう空気感にはなれていたのかもしれないですね。先輩とか先輩の知り合いがいるみたいな感じだったので、安心感があったかもしれません。
村野 わけがわからないですよね(笑)。うちのブランドは「かわいい」という言葉がキーワードのひとつですが、もともとはそれだけではなく、きょう横浜に行くなら、ぴちっと全身ハマトラで決めるとか、マリンスタイルにするとか、とにかくいろんなものが好きで自分なりのキーワードを決めて楽しんできました。
村野 ファッションに本気で進もうと思ったのは高校1年生くらいです。
村野 私はそれまで、ファッションと音楽、どちらの道に進むか迷っていたんですが、どちらかを選ぶなら、ファッションかなと考えるようになりました。音楽だと真面目に練習しないといけないし、まあファッションがそうではないということではないんですが(笑)、自分がわくわくするほうに行きたいと思い、ファッションに決めました。いつも遊んでいた仲のいい友だちとも、代官山に、そのころの代官山もいまみたいな雰囲気ではなかったので、いつかお店もてたらいいね──なんて話をしながら桑沢に向けて勉強していきました。当時ファッションを学べる学校といえば文化服装学院か桑沢デザイン研究所で、桑沢は学校が原宿に近いというのもありましたが(笑)、デザインからはじまった学校だということもあって、学校での学びを広く活かせるのではないかと思って(進学を)決めました。桑沢は試験がすごく難しいというのを聞いていましたから、受験前には予備校にも通いましたよ。

村野 私は1977年の入学で、当時ドレス科は50名の2クラスでした。そこには当時、思い描いていたファッショナブルともまたちがういろんなタイプの方がいらっしゃいました。大学卒業後、あらためてファッションに真摯に取り組む真面目なグループや、サーファーっぽい方、いろんなファッションの方がいて、とても明るくて和気藹々としていてすぐに友だちになれるような感じでした。
村野 平面構成の宮沢タイ先生はすごく厳しくて1回遅刻すると点数が引かれる感じでしたから、徹夜明けであろうが、かならず起きて出席していました。私は出席番号が後ろのほうでしたからぎりぎりでガラっと扉を開けて滑り込む感じでしたが(笑)、授業はすごく面白かった。
村野 私は1年生のとき、デッサンとかデザインとか、自分より巧い同級生を前に、あまり自信がもてなくて、自分でもグッとくるものがつくれなかったんですが、2年生のとき、自分のつくったものを先生が「すてきじゃないか、この服は」とほめてくださったことで大きく変わったんです。「すてき」といわれたことがすごく心に響いて、そういうところが自分にもあるんだと思うと自信がもてて、いろんなものが自分のなかから生まれてくるようになったような気がします。もしあの先生がいらっしゃらなかったらファッションの仕事にかかわっていなかったかもしれない。
村野 そうです。それまではとりあえず課題をこなしながら、本当にこれでいいのだろうか、と悶々としていたんですが、そのときはじめて自分もなにか生み出していけるかなと思ったんです。
村野 素材の選び方とか、ちょっとしたディテールの扱い方とか、ストーリーみたいなものがひとつの服に詰まっていたのではないかと、いまは思います。
村野 当時の桑沢は3年次に研究科といって、進学希望者には審査があるんですね。研究科では、いろんな企業に行って、それまでは自分のためにつくるだけだった服がいろんな企業の方と打ち合わせて制服をつくってみたり、工業用パターンをつくってみたり、いままでとちがうスペシャルなことをやらせていただきました。研究科は人数もすごく少なかったので、卒展にも向けてチームを組んで、ファッションショーのまとめ役もひきうけたり、舞台の構成をまかせていただいたり、より実践に近い学びでした。

村野 原宿という街がまだ私のなかでも大きな比重を占めていたのと、桑沢に来るファッションの求人の多くが大手か中堅だったんですね。当時はマンションメーカーからちょっと大きくなったようなブランドが新しくて面白い洋服を若者に対して打ち出していましたから、学校の求人だと自分にとってはわくわくするようなブランドが少なかった。そんなこともあって、いろいろ考えたすえに自分で門を叩くしかないと決意しました。
ちょうどそのころ、文化服装学院の友だちからミルクの求人が来ていたという話を耳にしたんです。ミルクは高校生くらいのときから好きだったし、あそこなら自分の感性も活かしてもらえるかもしれないという思いがあって連絡をとったんです。
村野 そうなんです(笑)。ひとみさんのお母さまに面接していただいて、ゴローズでアルバイト経験があるというようなことを書いたら「あんさん、ゴローズにいたんかいな」と(笑)。「うちとは真逆やないか」みたいなニュアンスだったはずですが、研究科の授業でつくった服を着ていったら、「ミルクのイメージに合っている」とおっしゃっていただいたので、ちょっとホッとしました。
村野 当時ミルクはアトリエで十数人が働いていました。こぢんまりとしたものでしたが、すごくありがたかったのは、ひとみさんのアシスタントというかたちではなく、生地選びからプリントや先染めをつくるところまで、最初から全部まかせていただいたことです。もちろん全部、MD(マーチャンダイザー)やひとみさんのOKをもらう必要がありますよ。でもたとえばコレクションをやるにあたっても、小物から全部、考えてみなよ、といわれて、自分のシーンだけは自由につくらせていただいたんです。自分の世界観をミルクのなかで表現できたのは大きな力になりました。
村野 プレッシャーを感じることもありましたが、とにかく服が好きでいろんな服をみてきましたから、たとえば生地屋さんや刺繍屋さんに、それは無理、できないといわれても、こういうものはすでに世のなかにあるんだからできるはずだ、と強く主張したこともあります。当時はいまとちがって、メールはもちろん、FAXもないアナログな時代でしたから色チップひとつつくるのでも、絵の具を単語帳に塗って指示していました。東洋インクの「日本の伝統色」というようなカラーカードはありましたが、それではなかなか厳しくて、自作したんですね。そのときは、白から黒まで、100の階調をつくるという桑沢の授業がすごく役立ちました。授業では白から黒までのあいだを100色ぶんのグラデーションで埋めるんですが、授業を経験したことで、ほんのちょっとのちがい、細かい部分を意識するようになりました。

村野 ブランド名の「ジェーンマープル」はアガサ・クリスティという推理作家の小説に登場するミス・マープルというおばあちゃんの探偵の名前です。ミス・マープルが最初に手がけた作品が『牧師館の殺人』(1930年)で、その舞台が「セント・メアリ・ミード」という村で、ここから会社名をつけました。もともと海外の推理小説は好きでしたが、セント・メアリ・ミードの情景とか、世界観のなかのおばあちゃんにスポットライトを当てることによって、年齢とか性別とかそういうものを振り切ったところにある精神性みたいなもの、少女性というとおかしいけれど、ある種のイノセントな部分などを出していければいいなと考えました。自分たちの洋服にも小説の物語や場面のように想像力をかきたてるところがあるといいなと思ったんですね。小説のミス・マープルは詮索好きなおばあちゃんですが、すぐれた洞察力をもっているし、そのような人物像を自分なりに昇華していけたらいいのかなと。
村野 私の根底には、クラシカルでトラディショナルなものがあって、それらを打ち破っていくような場面もあれば、清潔感や品格やインテリジェンスを大切にする側面もあります。服作りは視覚的なものはありますが、精神的なものもすごく大事にしたいという思いがいつもどこかにあって、私にとっては譲れない部分でもあります。服を着た人がしあわせになるものでありたいという気持ちが私のなかにはあって、そのなかからいろいろつくっていけばいいというような、当初は漠然とした考えだったと思います。具体的な部分をひとつあげるとしたら、イギリスの寄宿舎の制服のようなトラディショナルなスタイルが好きでしたから、それらの要素をジェーンマープルなりにかたちにすればよいのかなという気持ちもありました。

村野 あっというまにそんなになっちゃって。恵まれていたのだと思います。
村野 うちはコレクションを手がけるブランドではなかったので、ブランドを認知させるために協力していただける媒体と、タイアップみたいな形でブランドのイメージつくりをしていくほうがいいと思い、力を入れていました。『装苑』とは継続的にとりくんでいましたし、『Olive』や『CUTiE』もそうです。撮り下ろしをするのでも、ふつうのファッション誌やカタログ誌みたいじゃなくて、読者が切り抜いてとっておきたくなるような、心に残るビジュアルで、いままでにない誌面をつくりたいと思っていました。
村野 もちろん私の力だけじゃなくて、カメラマンさんやスタイリストさん、ヘアメイクのみなさんと「こういう世界観で」と話し合った結果だと思います。チームとしてすごく楽しい機会でした。いまの時代はデジタルでいろんなものができますが、あのころはフィルムで撮っていただいて、アガリもわからないまま進みますから、ドキドキしながらつくる緊張感がものづくりにも活かされていたんじゃないかと思います。
村野 ものづくりの経験を重ねて、生地の新しい加工とか、いろんなことに挑戦してみたくなったんです。ジェーンマープルは基本でありベーシックなラインなので、一歩踏みだしたものを表現するにあたって、新たなラインが必要になったんですね。でもつづけているうちにそういうふうにわける必要をあまり感じなくなりました(笑)。顧客の年齢層が上がったのもあります。
村野 譲れない部分はありますが、自分ではよくわからないんですよね。でもそういうふうにおっしゃっていただけることはあります。禁欲的な服だともいわれます(笑)。
私、少し前まで桑沢で教えていたことがあるんですね。「ブルーノ・ムナーリのファンタジア」というテーマでしたが、なにか目に見えないものであったり、感じるものであったり、知っているものと知っているものを重ねたときになにかちがうものが生まれてくることとかをテーマにしていました。いままでにないドキドキがあるものをつくっていきたいという気持ちはあるんです。そのためにもまず、自分がまずわくわくしないことにはじまらないと思うんですね。
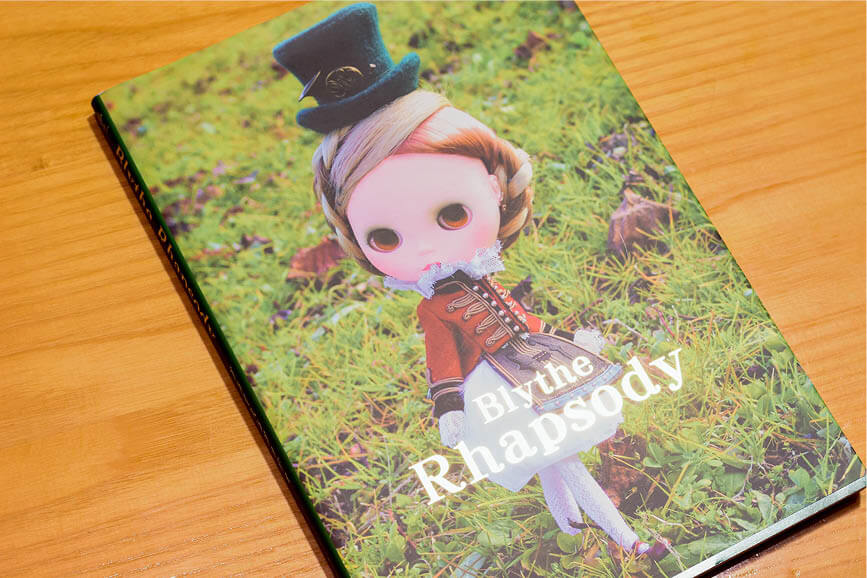
村野 本を読んだり、写真集を手にとったりすることもありますが、街やテレビや映画で見たもの、美術館に足を運んだとき発見したこととか、いままでの何気ない瞬間を抽斗に閉まってきたものを少しずつ紐解いて、これとこれを組み合わせるとか、経験値はすごく大きいです。
村野 いままさに次の秋冬でレミニッセンス(記憶改善現象)をどういうふうに上書きしていくかということをテーマしているので、そこに四苦八苦しながら挑んでいるところといえるかもしれません。私にとっての服作りはまず自分がわくわくすることなんです。これもう見たじゃんとか、これ着たじゃん、つくったじゃんというところから、それらをどのようにして2024年のムードに落とし込むかが課題なんです。たとえばプリントひとつとっても、毎シーズン外せないイチゴや王冠のモチーフも、色やカタチ、構成、素材、可能なかぎりあらゆる角度から検証しながら生まれる直感のようなものも大切にしたいです。慣れてくると、ついつい流されてしまいますが、そんなときでも、必要に応じて立ち止まって「ダメじゃんこれ」と判断することが大事だと思います。まずは人に伝えなければならない仕事ですから。
村野 すんなりとはいきませんね。ほんとうに才能がなくて、羽根なんかもうボロボロです(笑)。まれにすっと出るものもありますが、たいがいは苦労します。自分に納得できないタイプですから、一点(デザイン画を)描いても、いやちょっと待てよ、と。夜中に描いて家に帰って寝ても、朝が来たらやっぱりちょっとちがうといって捨ててまた一からということも少なくないです。100%できたことなんか一度もないし、悩んで後悔のくりかえしです。
村野 そうです。とくにうちは、長年手にとっていただいている顧客の方もいらっしゃいますから、定番であっても、かならずアレンジを加えます。お客さまのワードローブに並んでいる服に対して、新しい提案をさしあげることも、デザイナーとして大切なことですね。
村野 以前、桑沢で教えていたときにも感じたことですが、このところファッションは楽しむものであって仕事にするものじゃないという風潮があると思うんですね。一人一人が町の洋裁店で仕立てていた時代からプレタポルテ(既製服)が生まれて、70年代には原宿のマンションメーカーができて、少しずつファッション業界が大きくなり、大手が手がけるようになってから屋台は大きくなりましたが、ビジネスとして服作りを考える傾向が強くなった気がします。そのことももちろん大事なんだけど、文学や音楽と同じように、形や見た目だけではなく、着る人の心を輝かせるようなファッションがだんだん少なくなってきているのかもしれません。

村野 来年40周年なので、次にどうやってわくわくしたものを届けることが私はできるのか、いまはもっぱらそれしかないです(笑)。この先も自分がファッションに携わっていけるのであれば、ファッションがいかに人生の大切な部分なのかということを伝えていきたい。同じフリルであっても、着たときに風を感じたり、心に響いたりするのはどういうものか──、そういうものを追究していきたいと思っています。
村野 デザインは、人とかかわるものであり人をしあわせにするものでなければいけないと私は思います。それが一番根底にあるものかもしれません。ファッションも、その人がしあわせを感じられる一部分であること、それが一番大事だと思います。
村野 デザインにもいろいろありますよね。グラフィックやファッション、インテリア以外にプロダクトもあれば、パッケージもある。たとえ分野がちがっても、デザインは手にとった人の人生のすごく大事な部分に自分がつくったものや発信したものがかかわっていけるという大切な仕事だと思うんです。
(2024年3月24日 セント・メアリ・ミード アトリエにて / 撮影:濱田晋)