
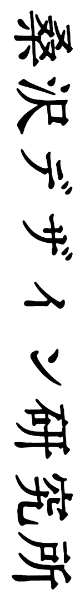
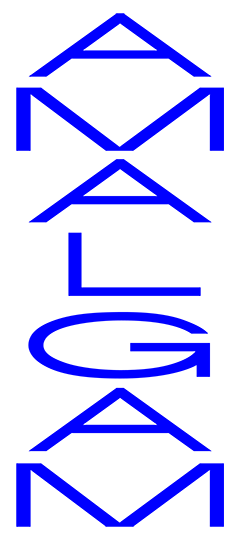
2025年に71年目を迎える歴史において多彩な人材を輩出してきた桑沢デザイン研究所の卒業生でも、川瀬陽太さんの経歴は異色といえるかもしれません。桑沢進学以前より携わっていたという映画の世界で、スタッフから役者へ転身し、いまでは年間10本を超える作品から声がかかるまでに支持を集めるにいたったキャリアの土台について、川瀬さんはまっさきに「映画が好き」であることをあげます。その気持ちをいかに持続させるか──。日本の映画界を代表する巨匠の大作から作家性を前面に押し出した自主映画まで、シリアスな人間ドラマからクセのあるコメディまで、いまや日本映画に欠かせない俳優のひとりとなった川瀬陽太さんにその極意をうかがいました。
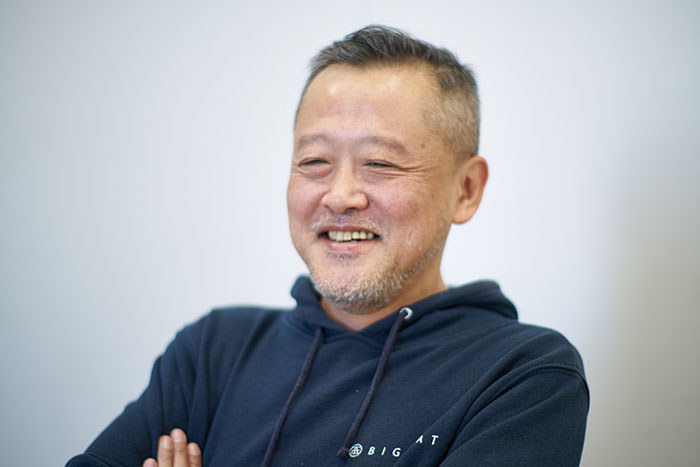
川瀬 じつは最初の受験では四年制大を受けましたが、うまくいかず、浪人生活のなかで絵が好きなんだからという理由で美大受験を志したんです。当時は第二次ベビーブーマー世代で、倍率もすごく高かったころで、藝大こそ受けませんでしたが、多摩美、武蔵美を受けて、浪人を重ねてしまうんです。
進学先としてはいちおうデザイン希望でしたが、動機は不純で、絵を描いてそれがなにかになったらいいな、というようなことでした。モラトリアムの時間がほしかったのかもしれません。ただ同じころ、自主映画の世界にも入っていたんですね。
川瀬 とある美術予備校に通っていたとき、同級生の女の子に誘われたんです。陽太くん、映画に興味あるんでしょ、とスタッフ募集が載った映画のフライヤーを手渡されたのがきっかけでした。彼女は誰かに頼まれて、その映画のフライヤーをコピーでつくっていたんです。受験が控えているにもかかわらず、浪人を重ねたフラストレーションもあり、映画の世界に入っていったんです。そんな状況で、ああ桑沢という選択肢もあるなと気づきました。これまた不純な動機ですが、武蔵美とか多摩美だと、少なくとも最初のうちは郊外のキャンパスに通うことになりますよね。受験のさい、アクリル絵の具をカラカラ(キャリアー)に乗せて、都心から反対へとぼとぼ向かった、さびしい想い出が僕にはありまして、であれば渋谷がキャンパスの桑沢も受けてみようかと。そうしたら、おかげさまで受かりまして、桑沢での学校生活がはじまりました。
川瀬 正確な年度は忘れましたけど、90年前後でした。
川瀬 グラフィックです。ただグラフィックに特別な興味があったというよりは、あのころ、美術でいうと、会田誠さんやヤノベケンジさんのような方が出てきて、アニメなりマンガなり、比較的身近なメディアとアートがくっつきはじめた転換期だったと思うんです。まだ日本も景気がよくて、『i-D』とかの日本版が出ていたころですね。『Studio Voice』もみんなが買っていたころですよ。
川瀬 もっというと、学校に行く、公園通り近辺にもレコード屋もたくさんあって、CSV渋谷がその象徴ですが、とにかくいろんなものに触れたという印象があります。それこそ渋谷系という言葉が出てきたときだったので、桑沢のある渋谷は立地としてはすごく刺激がありました。桑沢にはいろんなことに興味をもった人たちが多岐に渡って集まっていました。音楽ひとつとっても、60年代のを聴くやつがいれば、フランス・ギャルのような音楽がリバイバルしていたり、ファッション科の子もいて、フリッパーズ、ピチカートの時代でしたからね。
川瀬 (間髪入れず)ンなわけないじゃないですか。まあでも、ヘンなかかとの高い靴も履いてみたこともありますよ。そのときに確信したのは、ホワイトジーンズを履いちゃいけないということ(笑)。色黒の自分がホワイトジーンズにサイドゴアブーツだと、まるでムエタイの選手が白いジーパンを履いたみたいで。あのときのショックは大きかったですよ(笑)。
川瀬 まわりにはオシャレな子たちがいっぱいいました。僕も近郊とはいえ、子どものときから新宿や渋谷が活動圏でしたけど、やっぱ地方から来ている子の方が、ちゃんとオシャレしているんですよね。友人の、青山出身の中原(昌也)くんとかは、自分同様で、そうだよね、ここ地元だもんね、というような恰好なときがあるじゃないですか。それが桑沢のときのように、まわりにオシャレなひとたちがいると、なんか考えなきゃなあ、と思いますもん。その結果、勉強以外の刺激も多くなりがちなんですが。
川瀬 僕はもう劣等生だったと思います。そうはいいながら、現実的に課題をこなさなきゃいけないわけで、その一環としてシルクスクリーンなどをやらせてもらったのはいい経験でした。僕らのころはちょうど学校にパソコンが入るか入らないかという端境期で、級数表とかカラス口とか、そういうものを使っていたんですね。傍らでは、ネヴィル・ブロディのようなデザインが流行っていた時期でもあって、やっぱりMacがないとね、みたいな感じもありつつ、高かったのでもちろん買えませんけどね。大竹俊介という研究科に進んだ友人によると、研究科には1台あったらしいですけどね。彼は卒業後、スペースシャワーネットワーク等の仕事にかかわって、いまでもデザイナーとして活躍していますよ。
川瀬 飲み屋でのつきあいも多いですが、いまいった大竹は原宿にオフィスがあるので、たまに会いますね。

川瀬 絵を描くのはたしかに好きでした。でもそれ以上に映画が好きだったんです。そういう意味では学校でのなにかということでは、人的な影響がいちばん大きいかもしれません。人との出会いがすごく大きかったと思います。
僕はもともと俳優をやろうと思っていたわけじゃないんです。映画が好きというところからはじまりましたが、可能性を考えていろいろやってはいたんですけど、学校を出たあたりでしょうか、助監督のお話をいただくようになったんですね。「作り物」もやりたいという希望もあり、美術と演出を兼任するようなことになると、学校での経験が役立ってきます。特殊メイクの真似事みたいなこともやったこともありますよ。
川瀬 フィルム時代でしたから。自主映画、インディペンデントといっても、最低でも16ミリで撮らないと劇場にはかけられません。となると、それなりにお金を引っ張ってこられる、アクの強い人たちが目立ってきますよね。
僕の前の世代だと、いまは岳龍さんになった石井聰亙さんや塚本晋也さん。僕は福居ショウジンという監督につきましたが、福居さんの横には山本政志さんがいて、というような時代です。みんなそこで映画をつくっていました。
川瀬 邦画については、僕らがこの業界に入る前、80年代の角川映画のころにすでに「凋落」といわれていて、それはいまも変わらないと思います。技術的には、現在のようにiPhoneで4Kの動画が撮れるような時代ではなく、最低でも16ミリ──ということは現像費もかかり、それなりの機材が必要になりますよね。さらにいえば、それを使えるスタッフも必要という時代でしたから、その組閣ができない人間には映画は撮れなかったんです。
川瀬 その点で僕は、ひとりではなにもできないと思っていたんです。みんなで集まって知恵を出し合って、一個のプロジェクトを完成させるという作業が好きだということに気づいたんですね。それこそデザイナーをやっている友だちを見ていると、ひとりでちゃんと物事を進めたり、フリーランスや、自分で会社を起こすような人も多かったですが、僕はあまりその感覚がもてませんでした。本当にアクシデンタルな理由で俳優をやらないかという話になり、俳優部にコンバートしただけで、芝居よりも映画が好きではじめただけでしたから。桑沢に通っているときからそうでしたが、人に豪語できるのは映画が好きだということなんです。
川瀬 いまはライブハウス『WWW』になったシネマライズとか、桜丘の方にはユーロスペース、シネセゾン渋谷など数多くのミニシアターがありました。映画とは関係ないですが、都知事選で渋谷公会堂の前のところにトラックが横づけになったかと思うと、内田裕也さんが出て来て歌ったり、あのころの渋谷にいられたのはよかったですよ。

川瀬 福居ショウジン監督の『ラバーズ・ラヴァー』です。それが、また奇しくもいまはなきシネアミューズ、東急文化村の向かいの劇場でかかりましてね。96年かな。
川瀬 監督はそうじゃないといいますけど、あの映画には事務所に頼みづらいバイオレントな役やちょっとえぐい表現があったので、なかなか決まらなかったのだと思います。理由ではどうあれ、役者にしてもらった転機ではあります。
川瀬 それどこじゃなかったです。芝居もやったことない人間が、東京グランギニョルの飴屋法水さんとか斉藤聡介さんと、いきなりテンションの高い芝居をしなければならない。がんばるしかないという心情でした。でもできあがって映画が劇場にかかったときは、ひとつのものを生みおとしたんだという充実感があったのは事実です。
川瀬 このまま俳優をつづけるか、演出部に戻るかどうしようか迷って先輩に相談してところ、声をかけていただのが、いまはもう大監督になっちゃいましたけど、瀬々敬久さんでした。瀬々監督と出会いを経て、いまに至ります。
川瀬 わりかしふらついている人間もいましたよ。なかには、いまもアーティストとしてやっている中島崇もいれば、カレー屋さんになったやつもいる。千駄ヶ谷のヘンドリックスというお店です。若林(タケシ)というんですが、彼は同級生の中村(ジョー)とハッピーズというバンドをやっていて、中村はいまでも曽我部(恵一)さんなどとライブしています。音楽系ではスカパラでギターを弾いている加藤隆志もそうです。
川瀬 いまほど世の中もカリカリしていなかったですからね。なんか大丈夫──みたいな感じはあったと思います。
川瀬 そうなんでしょうね。僕は結果的に俳優になっただけで、なろうなんて思っていたら、到底なれなかったと思いますよ。
川瀬 なりたい自分があったらちょっと無理です。流された結果ですから。それこそデザイナーになるでもなんでもいいんですが、一念発起して東京に出て来られる方はすごいと思います。僕なんか地方にいたら普通に、ワンボックスにエアロパーツつけて家族7人で暮らしていたんじゃないですか(笑)。
川瀬 (うれしそうに)そうですね(笑)。あいつらにも旅に連れていってもらっている感覚があって、自分の主体性がそこまで強くなくてよかったな、と思う理由です。ただ出会っている人間は正しいというか、ライトスタッフになっている気がします。それはちょっと誇れることかもしれない。
川瀬 先日、ハーバード大で日本映画を研究している知り合いで、もともとニッポン・コネクションを立ち上げたメンバーでもある、アレクサンダー・ツァールテンという人がいるんですが、彼に「うちに台本たまっちゃって困っている」と漏らしたら、「それならハーバードが所蔵するよ」といわれて驚きました。僕自身はたいしたものじゃないけど、自主映画やVシネという日本映画の変遷を経験しているのかもしれないとは思いました。
それに、1990年代からゼロ年代初頭にいたるまでにつくられた日本映画は、メジャー作品も含めて、フィルムアーカイブが存在しない作品がすごく多いんです。バブルが弾けて、無数にあった横文字の制作会社がツブれた挙げ句、素材をどうにもできなくなり、失われた作品が多々あります。黒沢清さんのようにごく少数の作家の方がアーカイブでみられているくらいで、Vシネマでいえば僕らがつくってきたVHSはほぼ廃版です。これらの作品は、現場ではフィルムで撮影していますが、納品はビデオなのでフィルムがあったとしても未編集で上映できないんですね。ましてや、東京現像所も閉鎖になってしまい、ひきとりに来ないフィルムが山のようにあるわけです。ひきとりたくても、会社がないからどうにもできない。僕はたいしたことはできないけど、映画評論家の寺脇研さんに連絡して、なんとかならないのって。それで幾ばくかはフィルムセンターに寄贈されたみたいです。

川瀬 40です。
川瀬 先輩からいわれていたんですよ。30代は地獄だぞと。でも40になったらなんとかなると。
川瀬 俳優のメインロールは20代だったりとかすることが多いじゃないですか。
川瀬 それが5年、10年経って30代になると、それなりにいろんなものを残してきたはずなのにゼロカウントになるんですね。「30代は地獄」というのはそのことに自覚をもてということだと思います。だからといってがんばりようもないですけどね。俳優は待つ仕事でもありますから。
川瀬 冨永(昌敬)くんの『ローリング』(2015年)だとか『シン・ゴジラ』(2016年)前後かな。でもそこまでいくと、利口なヤツらは辞めて全体のパイが減って、ただ残っていただけなんですよ。ちょうど40超えたあたりから、どこの現場に行っても、どこそこの現場で一緒でしたと、スタッフなりキャストの方に声かけてもらえるようになったんですね。そのとき、あっ、やっと職場に認められたのかもしれないと。だから自覚が芽生えたのは恥ずかしながら40代です。
川瀬 佐藤慶みたいにやれということかと思って「私は──」みたいな声を出しました(笑)。
川瀬 きっと冨永くんもそう思ってくれたんでしょうね。映画自体はすごくヘンな話だけど、ノワールの要素もあるし、冨永くんらしいオリジナリティのある作品だったと思います。そこに触れたこと、もうひとつ転機といえば、その前の富田克也たちの出会いですかね。『国道20号線』(2007年)をみた衝撃で、『サウダーヂ』(2011年)という映画に彼らが呼んでくれて『バンコクナイツ』(2016年)にいたるわけですから。いまも新作、あいつらは粛々と待機中ですけど、それまでにない映画づくりのかたちを模索していて、いまの業界の内側のセオリーで汲々としてやっている人たちばかりじゃなくて、外の世界を感じる映画をつくっているヤツらと一緒に走れたりしたから、人が気づいてくれたのかもしれないです。
川瀬 『サウダーヂ』が2011年なので、彼らに直接会ったのは2009年とか10年ですが、僕らが映画をはじめた90年前後の雰囲気をもっているヤツらにひさしぶりに会ったというのを実感したんですね。彼らは空族というチームをつくって、それで映画をつくるという。誰かが手を挙げて終わったら解散する一般的なやり方じゃないですよね。作家集団としてやっていくんだと。これは90年代にはまだいた、映画を志向しているフィルム時代の人たちの感覚に近かったし、運命共同体でもある。次作もすでにうっすらと声がかかっているんですけど、あいつらとやるとなると2〜3ヶ月かかりきりになるのか(笑)と思いつつ、それを待っている自分もいるんです。声かかんなかったら、それはそれでさびしいですし(笑)。
川瀬 でも『サウダーヂ』なんか、出演していた田我流がアーティストとしても世の中に出ていって、映画が総合芸術であるということをちゃんとしめしてくれてもいると思うんですね。ある部分は政治的でもあるし、ある部分はエンタメでもあることをちゃんと標榜してやっている自主作家だと思います。いまは映画がエンタメに大振れしている感じするんですよ。それもわるくはないんだけど、そればっかりも楽しくないかなというのは、老害的な意見かもしれないですけど、ちょっとありますね。

川瀬 ショート映画などが話題になったのもそうですけど、みんな時間がないし、興味の対象が多岐にわたっているからそうなるんでしょうね。もっというと、僕がたとえばいま桑沢に入学したら、映画をしていたかといえば、自信ないですもん。
川瀬 『ピノキオ√964』(1991年)という福居さんの1本目の長編にスタッフとしてかかわったんですが、エンドロールで自分の名前が上がってきたときに決まった気がします。映画の中に入っちゃったんですよ、そのときに。
川瀬 『鉄男』でもなく(笑)。ピストルズに対するディスチャージみたいなものかもしれません(笑)。もともとメインストリームではないのかったものが、瀬々さんとの出会いで本流に触れたことになるのかもしれません。
川瀬 いまでも憶えていますが、新宿のいまはなきとある喫茶店で「おまえさ、どうせできないんだから」と瀬々さんにいわれたんです。これ以上の殺し文句ないですよね。だって、できなくたっていいってことじゃないですか。だけど、おまえが来てくれりゃあ、という話じゃないですか。それはちょっと意気にも感じるし、そんな自由な世界があるんだとも思いました。それがたぶんプロになるか否かの瞬間だったと思うんです。ここでもライトスタッフに会えていたんだなという気はします。
川瀬 自由ですよ。瀬々さんの口から直接聞いたわけではないですけど、自分が依頼しているのだから役者に期待すべきだろうということなのかもしれません。瀬々さんはご自分でも、あるいは井土(紀州)さんと共同でホンを書かれることもありますが、昔よくいっていたのは、それ(脚本)を放り投げるようにしたいんだということでした。事件をあつかうことが多いからかもしれませんが、たとえばニュースをみていて、誰かが誰かを殺しました、動機はこうです、といわれても、いや本当にそうかと。動機なんて、そんなふうにわかるのだろうかということにフォーカスがあたるのが映画だと瀬々さんはおっしゃっていました。もっといえば、撮ったあげく、わからないということに触れる作業。本当のところはわからないということに触れる作業にどれだけ真摯に向き合えるかが大切だという気が、瀬々さんをみているとしてきます。

川瀬 おかげでいちおう生活できるぐらいにはなりました。
川瀬 苦しいなんてもんじゃないですよ。なにもないときは本当になにもありませんから。
川瀬 それこそデザイナーの友だちの下請けみたいなことをやったこともあります。指示されたことをこなす仕事ですね。あと、手を動かす仕事でいえば、テーマパークの山車(フロート)の色塗りとかやっていました。20代から30代に入ってもやっていましたね。
川瀬 生活不安はつねにありましたけど、映画の世界にいても、いまおか(しんじ)さんとか、仲間うち合わせて20円みたいな時代もあったんで(笑)、どうせダメだしみたいな感じでした。
川瀬 必ずいっているのは「つづけていれば絶対、どうにかなります」ということです。ただ「なりたい自分じゃないかもしれません」──この一点だけです。たとえば松田優作さんとか、こんな人になりたいとかっていうのがあったら非常につらい仕事だと思います。僕は本当になりたい自分がなかったからつづけられたし、地方に仕事で出かけると、(この仕事を)辞めたヤツに「迎えに行くよ、飲みに行こうよ」と誘ってもらって、そいつが乗っている車がベンツだったりするんですよ。そっちのほうがいいな、と思うんですけど(笑)。でもそれだけ、自己実現の気持ちが強い人たちがたくさん来る職場なので、ほかの仕事でも成功できる人はいっぱいいると思いますよ。だけどこの仕事をつづけるのって、どれだけ映画が好きかだし、好きであれば、興味をもってやれれば、人から規定される川瀬陽太として認知されて仕事にはなるんですね。
川瀬 それでもいいのであれば、ということですよね。とくに日本にはアンチエイジングの信仰のようなものがある気がするんですね。女の人に年をとらせないというか、その子と似たようなスペックをもっている若い子にロケット鉛筆のように役をガチャッンコするじゃないですか。カワイイの国なので、そうなのかもしれないですが、僕のなかではカワイイやイケメンの話ばっかりしているとバカになっちゃうよ、と老害らしく思うことはあって、最近でもやっぱり池脇千鶴さんとかちゃんと年をとれる人がいるので、そういう人がどんどん出てくればいいなって思っています。
川瀬 それでも作品にとってその役は必要だから、誰もが田中泯さんや、樹木希林さんに仕事を頼んできたわけです。僕はスタッフが一緒に年をとれればいちばんいいと思います。監督だって年をとっていますから。そこらへんに妙な矛盾があるんですよ。
川瀬 そうかもしれないですね。いまでは映画館はキラキラ系の予告篇ばかりですが、無理がありますよ。もちろん商売だからやっているというクールな判断もあるとしても、配信という第三極が出てきて、海外の面白い作品がいっぱいみられる状況になってきていますしね。以前とある現場の立ち上げのさい「これ全世界配信ですから」ととくとくと語った方がいらしたんですけど、僕は「それ水道管が通ってるだけで蛇口ひねらないと水は出ないよ」と思っちゃったんですね。どうせ全世界配信なら、日本のよさというとヘンな言い方になっちゃいますけど、アジアの一ヵ国としての日本で撮れた映画のほうがいいと思うし、東南アジアや台湾で活動している富田(空族)とかのカメラの前に身を置いてみるとか。内向きの文化ばかりじゃやせ細る一方だと思っています。
ただ僕は日本映画をめぐる状況に、そこまで楽観も悲観もしていません。端的にそう考えることに意味はなくて、次どうするかということだけを考えて、世間にどう思われていても、もう知らんと(笑)。最近の合い言葉ですよ。「おれはもう知らん」(笑)。(了)
(2024年12月18日 桑沢デザイン研究所にて / 撮影:塩田正幸)